●その1
今井路子さんの『自然流おいしい食事』(講談社)を読んでいたら、次のようなことが書いてあった。
《農業用に使用している油とまちがえて天ぷら油を噴霧したことがあって、そのとき、虫がつかなかったとか。まだ、試験段階なのでなんともいえないが、これが効果的なら、廃油の利用にもなり一石二鳥だって。》
ところが、『近世秋田農書の研究』(秋田文化出版)によれば、
《実はこの「羽州秋田蝗除法」が出た明和のころには、害虫防除に油を使うということは全国的には一般化していなかったのです。全国的に一般化するのは、大蔵永常が文政九年(一八二六)に『除蝗録』という農書を書いて、それが全国に普及するようになってからです。ですから、秋田ではそれより約六十年も前に、油を使って稲虫を駆除するという方法がとられていたということです。》
たぶん、化学肥料が普及したために、こうした昔の技術というものが伝達されなくなったということなのだろう。
こうした本を読んで考えさせられるのは、平凡な言い方になるが、昔の人の偉さである。害虫を防除したり、生産をあげるために、全国から農書を取り寄せたり、また現地に行ったりなどして、研究していることである。
もちろん現在でも、農業試験場だけでなく、わたしたちの知らないところで研究したりしている人はいっぱいいるのだろうが。
(2002.04.27).
●その2
江戸時代、お蔭参りなどをのぞけば、他藩との民衆次元での交流はきわめて制限されていた、というのが一般的ではないだろうか。
ところが、この本によれば、今の出稼ぎのような行為があったことがわかる。
「老いの故事」についてふれ、次のように書いている。
《津軽の農事についてかなり知っているのです。例えば、「津軽碇カ関より向き、黒石、弘前の富国中と唱るハ民の知る処也。此辺迚も下国なれば我国(秋田のこと)より田打も遅く、水を掛けずして田打、悉く天日を入れて後、又横槌を用ひて打砕き、夫より水をかけて代を掻く也」とあって、全てのことは時期的に秋田より遅れて農作業を行っていて、そのためにいろいろ苦労している、というように書いています。つづいて「此故に、田植も我国より遅し、我国の植場過に国の民田植手間取に行也」とあります。つまり、津軽は秋田の田植えが終わってからなので、秋田の百姓が自分の田植えを終えてから、津軽の田植えに手間取りに行く、ということです。
これは今まで藩政史ではほとんど注意していなかったわけです。農民なんていうのは、限られた中にいて、その中で年貢をとられていたり、田にしばりつけられていた。実際その通りなわけです。ところが農民だってやはり自分の生活を豊かにするために、知恵を働かせるわけです。津軽の人は人手がほしい。短い時間でどっと田植えをするためには、人手がほしい。それで秋田の農民は自分の田植えが終わってから、手間とりに行って稼いでくるのですね。そういう知恵をちゃんと持っていたのです。そういうことを、藩政文書にはないが、重兵衛は書いている。》
(2002.04.27)
|
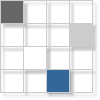
![]()