 |
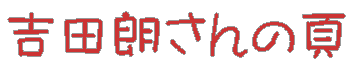 |
|
|
 |
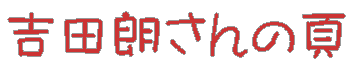 |
| 2 ���s���ΊC�̉��́i�S�j | ||||
|---|---|---|---|---|
�i��j�n�c��̖S��
�@�Ƃ̑O�̃J�G�f�����ɓ��ɐF���܂��Ă����B������̈�������ł��A�G�߂��߂���ƃG�j�V�_��Ԃ��������Ԃ�������U���̂ł���B���܂�O���͖��邢�����ɗh��߂��A���ǂ������̕��Ɍ������Ċ����ӂ�n�߂��̂ł������B
�@�u�R�g�D�j���t�v�Ə̂��ꂽ�c���j�ώ̒��]�����t���A�E�\�œ����O�S�c�ȁB����ɃA�O���������ď���ł�ʂ����͂��̒|���������A���ɏX�Ԃ����炵�ސw���������B
�@�u�t���������䂭���̂̋����͂Ăāv�i�㉓���j�B�H�c�s�̈��w���������傪����������Ă����B���N���[�g�^�f�A����ᔽ�̏���ŁA�ЂƂ��э����̐M�������Ȃ��������}���t�͂Ȃ���̂悤�Ɏx�����������A�����鑒���̂��Ƃ𗁂тĊ��������B
�@������͋t������܂Ԃ����t���ɓ]�����悤�Ƃ��Ă����B���ꕅ�������̂̉^���́A�{���G�ЂƓ������̂Ă���B�����ē{��̎����͗��c�f���Ȍ������B �嗤�ł́A�ސw�����|�����t���͂��ߎ����}���{���A���Ȃ��Ȃ������̌��ł�͂��Ă���͂��̒����w�������A���E�����̂��ƁA�p���ׂ��ߌ������炪�����A�Ռ���^�����B�V����L��͎��Ȃ�ʌR���̔��C�Ō��h���A������@�ɒ����S�y�͖���^���ɂƂ��đO���I�I�~�̎���Ɍ�ނ����B
�@�V�c�̌R���ƎЉ��`�̌R���ɂ��āA���͑O���ɏ���������Ȃ̂ŁA�����̌R���͐l������R�ł��邩�ǂ������̂��A���ɂ߂悤�Ɛ[������Ɏ����X�����B�l���̌R���́u�I�H�D�v�̋쒀�͂̕��m�̂悤�ɘJ���҂�w���ɂ͏e�������Ȃ��͂��������B
�@���q�̕��@�̊J���܂���Ɂu�p���͓��`���Ȃ���Ȃ�ʁv�Ƃ���A���̑��́u���킭���Ȃ�A���`�l���ɓK����`�����ɑ�������́v�Ƃ������B�u�ނ�m��Ȃ�m��ΕS�킵�Ċ낤�ׂ��炸�v�͒N�ł��m�鑷�q�̂��Ƃł��邪�A�����ł��܂����̑��q�͎��p�I�ȌÓT�Ƃ��Ē��d����Ă���Ƃ����B
�@�����̎w�����͉��������������̂��A���́u���`�l���v�̏펯��Y��A��������ԑf��̊w���A�s���̒��ɐ�ԂƑ��b�ԂŏP�����������B���̉f��������Œm�����ЂƂ̃V���b�N�́A�����炭�͂��炭�Â܂�Ȃ������ł��낤�B
�@�l�����������͂��̌R�����l���Ɍ������Ĕ��C���E�l���s�Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͒N�ł��낤�ƐM������Ƃł������B�u���R�̏��_�v�̑����Ђ����������m�̊�͑����ɂ�����Ă������A�e�𗐎˂���p�͊��S�ɋw�G�ɑ��邻��ł������B�e���Ɖ���̉����������ю��҂����l���^�Ԋw���Ə����ւ�����́u�����v�̉p�Y�̃R���g���X�g�����Ƃ���ۓI�������B
�@�u���얯��v�i����s�j�����ܓ����́u���̖\�s���A�������A�l���y���̎v�z�͐`�̎n�c��ɕK�G����v�Ə������B���y�j�Ƃł����铯���a��劲�ɂ��A�n�c��́u�g�͍��т��y���v�i�l�\���N�O�̐푈�ō��������肽�Ă��A���Ƃł�����j�Ƃ����l���}���҂ŁA�Ō�̌���ł͓G�̕ߗ��l�\���l�������߂ɂ��Č������߂Ƃ����B�܂����v�Ɖ����V�肵���w�҂�߂��A����������߂ɂ��A�S�����炻���̊w�҂̖{���W�߂ďĂ��������̂ł���B
�@�����ł͂��n�c����ĕ]�����Ă���Ƃ������Ƃ����A����������������^����e�����A�w���҂����Y���A���������v����Ƃ��������|������z�����i�́A�n�c��̖S�삪���ڂ����Ƃ����l�����Ȃ��B
�@���Ă����͓��������A�����̍��A�����A�����F�D�̉^���Ɏ�g�B�����̎w�����͂���������ɗ��������̂ł���B�����ɂ͎Љ��`�͂Ȃ��A�l������R�͂��̖��̒ʂ�̌R���łȂ����Ƃ��A���̓��A�S���E�Ńn�b�L���Ɗm�F���ꂽ�̂ł���B
�i�j�j�ł�����̂́u�d�T�v
�@�u�p���͓��`���Ȃ���Ȃ�ʁv�Ƃ̑��q�̕��@���炢���A�푈�����͐��`�l���ɓK���Ƃ͎v���Ȃ��B���̍ł�����͍̂L���E����̌����������B
�@����ł͐������̐V���킪�o���������A���̍ł�����̂́u�d�T�v�Ɓu�����v�������Ƃ�����B
�@�d�g�T�m�@�������ƕ��ׂ��镺�킪�ǂ����A�s��̓��܂ł���𑀍삵�A�͓��Ńu���E���ǂ��ɂ�݂Ȃ���A���e�i���Ă������ɂ́A�₩�ɐM�����������Ƃ������B���A�d�g���킪�e���̊�n�̍ŏd�v����Ƃ��ċ����悤�ɋ���ȃI���������ϑ����Ă��錻��́A���܂��ς��Ȃ����Ƃ�����Ă�����̂ł��낤�B
�@���Ԃ��Ȃ������ɂƂ������A���͑��̎Q�d�����u�C�R�̔��ȁv�i���܈�N�A���Ŋ��j�Ƃ����{���o�����Ƃ��A���m�Ȉ�d�����͂����ǂ�ł��₵���ɗ܂��|���|���������̂ł������B
�@�u�d�T�����������{�͗��_�I�ɂ��Ƃ����Ă����Ǝv�����A���S�ɃA�E�g�E�����W�i�p�͂ɂȂ�ʁj����Ă����v�Ƃ���������͂܂��[�������Ƃ��āu�|�������S���{�����Ă݂Ă��푈�ɂ͉���̖��ɂ������Ȃ��������Ƃ͓d�T��������ė]�肪�������v�ɂ͈��R�Ƃ���������Ȃ������B���{�͑�`�ɂ����Ă܂������A�d�T�ɕ����A�����ɕ������̂ł��������A�C�R�̍���]�����ꂭ�炢�̂��Ƃ�m���Ă����Ȃ�A�Ȃ��푈���n�߂����Ɠ��ɗ����̂ł������B
�@�푈�̑S���Ԃ�ʂ��A�͑D�A��s�@�A�����͂̕ʂȂ��A�܂���n��A�������킸�A�܂����J�A����̍��ʂȂ��A������U�h�p�̏d�v������Ȃ������̂́A�u�d�T�ł������v���Ƃ́A�l�N���J���̊C�R�̐����ŋ��R�Ȃ��玄�͂��̉Q���Ōo�������̂Ŏv�����������B��������퍑�A�����J�ɏ\�N��\�N�̒x�����������ꂽ�B
�@�J�펞�A���{�R�̓��[�_�[���܂������������Ă��Ȃ������̂ɕČR�͎��p�����Ă����B�~�b�h�E�G�[�C��̔s�k�̓��[�_�[�������̈�ɂ����B���{�C�R�͂��̂Ƃ��d�T����͒ʐM�w�Z�̒��ŏ���������Ă���ɂ����Ȃ������B
�@�C�R�͕ČR�Í��̉�ǂɖ�N���������A���̕З����A���܂Ȃ��Ŕs��ƂȂ����B�C�R�Í��͓����Ƃ��Ă͍ł��i���������̂Ƃ���ꂽ���A�ČR�͓��{�Í��̉�Nj@�������Ă����̂ł������B�C�R�Í����s�o���Ƃ����͓̂��{�̈�ʉȊw�����̃��x���S�̂��Ⴉ�������Ƃ������̂ł������B
�@�Ȋw�����̒Ⴓ�͍q��͂�n��ɂ��Ă����B��w�����u�ɂ����Ă͕ĊC�R�ɎO�\�N���x����Ƃ��Ă������Ƃ����Ȃ������B
�@�͋��̂������͈Í����A���̉��ɒʐM���A�����ĒʐM���̉��͓d�����ł������B�����͂������ɏo�����ĘA�����Ƃ荇��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�Í����͉�ǂɂقƂ�ǓO�邾�����B�ʐM���͖T��ɖZ�����A��M���������̂܂܂̈Í��d�͂����܂����ƂȂ���ł������B
�@�d�T�͌R�͂Ɨ��n�����ʂ���̂ɋ�J���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��s�@�ƎR����ʂ���̂��ނ������������B��ґ���B29�̍��ʂɂ������̌o���ƘZ�����K�v�ł������B
�@�C���̋@��������͂̎��ʂ͂炩�����B���g�T�m�@�͂Ƃ��ɐ��\���悢���Ƃ����������A�T���Ċ��x�����������B
�@�d�T�͉~���ɑ��삷�邽�߂ɑ��d�M�@���ŗǂ̏�Ԃɂ����̂ɑ���̘J�͂Ǝ��Ԃ��K�v�������B���܂ɂ��Ďv���A���ꂩ��̋@��́u���{�����v��u���Łv�u�Z�F�v�u�����v�Ȃǂ̐��삵���A���ׁ\�������͖��������킾�����̂ł���B�����Ό̏Ⴗ��̂Ŋ͂͏C���ɋA�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@������A���͔����㗤�Ō��̗n����W����������B���̈���͂��v�������Ă��Ô��ł������ɐł���B�i�u�H�c���啶�w�v15���A1989�E10�j
|
||||
|
||||
| 3 ���s���ΊC�̉��́i�R�j | ||||
|---|---|---|---|---|
���A�u�T�[�J�X�̉S�v������
�@�P�@����s���̈��
���]�̂悤�ɐÂ܂�~�̗Y����͌��������Ƃ��ě����̂悤�ɐ肽�����g���Ă���B�������A��㔪���N�̎t���́u�\���t�v�̑��ꂪ���܂�ė������ȍD�V�������A�ʂ���킹���B���䂽���͌��̊ݕӂɌQ�ꂩ���n�蒹�B�J����E�~�X�Y���A�����������ڂ������Ă���B
��͑S�������A�������ܓ�����z�R�����������B�g�~�Ƃ������ُ�C�ۂ̋C�z���Z���������B�������A�V�C�͐\�����Ȃ����������S�͐���ꂷ����ƂĂȂ������B�S�݂͂���܂���B�����j���������A�����������B
�@�����͋^�f�܂݂�̐��{�����}���A����ł̐������������Ă��邱�ƁA�H���ǂ��Ɍ����ăj���[�X�͂��Ȃ炸�V�c�́u�����v�����������A�s���w�������܂邱�ƁA�Ȃǂł���B
�@���肵���픚�n�i�K�T�L�Łu�����v���N�������B�����̎s�c��{��c�Ŗ{������s�������Y�}�c���̎���ɓ����u�V�c�̐푈�ӔC�v���m�肵���̂ł���B�u�V�c���d�b��̏�t�ɉ����āA�I��������Ƒ������f���Ă���Ή������L���A����̌����������Ȃ������̂́A���j�̋L�q�Ȃǂ��疾�炩�v�Ƃ������̂������B
�@����́u�V�c�ӔC�_�v�ւ̈�ł��������A�����Ɍ��_�̎��R�Ɩ����`�ɂ��čl��������ϋɔ����ƂȂ����B
�@�I�����_��̒���͂����܂��U�{���̘U���Ђ����肩����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B�����}���A�͑傠��ĂŔ�������������߂���A���A�ږ��C����߂����肵���B
�@�����}�́u�i�V�c�́j�a����l����ƁA����������Âȑԓx���Ƃ�ׂ��������v�Ƃ����A�a��̏�ɂĂ��˂��Ɂu���v��t�����B�u��Áv�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��悭�킩��Ȃ����A�����}�̂����߂̃X�L�����_���X�ȏ����������u��Áv���Ƃ͎v���Ȃ������B���Г}�͎����}�Ɠ������u�����P��v�ɓ��������A���Y�}�͂������x���������]�������B���j�F���̍��͂��̂܂܌����̍��ƂȂ��Ă����ꂽ�Ƃ����悤�B
�@����A�E���́A�������猧���A��B�e�n�A������܂œ����������W�������B�s�����O�Łu�{���o�Ă����v�u�����v�u�����{���v�Ȃǂƃo�����������������B���u���Ă���x�@�ɂ��������������A���̖����`���ւ���������Ȃ����肳�܂ɖ{���s���x�����}���ɍ��܂��Ă������͓̂��R�̂��Ƃł������B
�@�{���s���ւ̌���͎莆�A�n�K�L�A�d�b�A�d��ȂǓ��ʂɂ̂ڂ����Ƃ����B�i���̂��A����S�ʂ̂����R�c�͈ꊄ��Ƃ̔��\���������j���܂ł��s���̗E�C���������ق������������B���ܕS���̈�̌���ɂ����Ȃ����A��܂���A�E�C�Â���ꂽ�͎̂��������̂ŁA����̂���ŏ����������̎��������B
�@���̒��̑�n�̂ʂ������
�@��ɐ��߂�ꂽ������
�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����B
�@�g�~�̉͌��ɗV�Ԏq���
�@�i�K�T�L�̋�a��]����
�@�����ĂقȂ�Ȃ�����B
�i�ŏI�A�j
�@����ᔻ��������Ȃ����������O�̓��{�͖\�����Ă������B���ΐ��}��ᔻ���͂����������A���ʂ��悤�Ƃ��邢�܂̓��{�̕����͖����`�����Ȃ��Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�ɂ����Έӌ��Ɏ��������ނ���S�̍L�����ق����B����s���̈�͒����u���a�ʂ���v�̋M�d�Ȍx���������B
�@���l�l�N�l���A���̊͂��T�C�p�����Ɋ�`�������̖�A��P�����萦�����퓬�ƂȂ����B�������ɒD���Ă����B�T�C�p�����͊C���̕K���̖h�q�ŁA�܂��͂��̂����悤���邽���A����邩������Ȃ��Ƃ��̎��A�v�������̂��B���ꂩ��A�O�J����A�T�C�p���͋ʍӂ����̂������B
�@���̓�������{�̔s�k�͔������Ȃ��ɂȂ����Ɨ��j�͋L���Ă���B���̂Ƃ��x�ߎ��ς��n�߂������߉q�Ɩ،˓���b�A�c���̈ꕔ���푈�̎��W��ɂ��Ęb���������Ƃ����B�܂����l�ܔN�A���̑����߉q�����͔s��͌���I������ƏI���i�������Ƃ��V�c�́u������x��ʂ������Ă���v�Ƃ͂˂̂������Ƃ��悭�m������j�I�����Ȃ̂��B����s���͂����̎����ɂ��Ƃ����Ĕ��������̂ł���B
�@����U�h��O�ɂ��Đ��_�����̌��ʂ��V���ɂ̂����B
�@�i��������88�E12�E7�j�Ő����v�ւ̕s�������債�|�����t�͌l�E���p�[�Z���g����O�܁E��p�[�Z���g�Ɏx�������}���B���ɕs�x���͎O��E���p�[�Z���g����l�E�Z�p�[�Z���g�ɏ㏸�����B�����͉��̃T�����Ⴀ��܂����A�A���ƃ��`�ł��܂���Ȃ����Ƃ�\�������̂ł���B�i���̌ナ�N���[�g�^�f���L����ƂƂ��ɐ��_�����͂���ɉ��~���A�O���̂m�g�j�̔��\�ɂ��ƁA���t�x�����͈�Z�p�[�Z���g�B�����V���̂���͈�܃p�[�Z���g�ɉ��������B�j
�@�h�����鏼�c�K�v�搶�i�H�c�s�E���c��@���r�Ɂu���a�v�̍Ō�̓��͂��ɂȂ�܂����A�Ƃ������������Ƃ�����B�\�̏��߂������Ǝv�����搶�́u���Ƃ������ς��v�Ɨ\�������ĂĂ��ꂽ�B�������T�Ԓx��̈�㔪��N�ꌎ���������̓��ƂȂ����B�덷�͈�T�Ԃ������킯�ł���B���̖�A���ǂ��͎����قŐV�N�����\��ǂ��肨���Ȃ����B�k�_�����A�J���I�P�����������т������B�s��c���̉����a�q������������A�������������̂͐E�l�������B��Ј��A��s���������B�����������������͍̂��ƌ������������B�u���a�v����E�o���������������Ă��A�u�̕����ȁv�����l����Ƃ��������[�h�ł͂Ȃ������B
�@������A�����̔������炢�A�����ɉ������d�ˁA����ł����炸�A���Ƀ��m�����킹�ċ��s�̌���������ł��������A���̊ԁA�V�c�͉������Ȃ��u���ڂ������v�z�N�A�����s�������炩���I������Ƃ���ŗՏI�Ƃ����킯�ł���B���ꂪ�u��������ɍl���Ă����v���X�g�E�G���y���[�̎��������B���̖�A���茧�̉̐l�́u�픚���̈�l�ЂƂ��������ˉJ�����Ă��菺�a�ʂ��v�Ƃ������B
�@�����j���͂��������ڂɋN���u�v�V�s�����߂�����v�̃`���V�܂��������B�����ɂ͒����𗧂ĂĂ���Ƃ����������B�������u����v�̍��O���o���̂łǂ�ȉe�����N���邩�Ǝv�������A���̒����͌ː��S���\�A���̂����͕��r�ƂȂ����̂ł���B
�@�A��Ă���Z�K���̉Ƃɓd�b�����Ƃ��돬��̑������o�āu�e���m�[�w�C�J�Ń}���K����Ȃ�����܂�Ȃ��v�Ƃڂ₢�Ă���B�V�c�����҂��͒m��܂����A�V�c���q�ǂ��ԑg�܂ŒD�������Ƃ͒����L�����Ă��邱�Ƃ��낤�B�}�X�R�~�͘A���u�V�c�Ђ��v�������B�u�V�c�v�Ɉُ�ȔM�ӂ������B�قƂقƂ��肵�Ď��͐e�q������ς邽�߉Ƃ��т������̂����A���ňꖇ�̎��Ђ�n����ċA���ė����B�u���l�̂��ߏ㉉���~�v�Ƃ������B
�@�l�Ԃ����玀�͂�������Ă���B�A���͔߂������Ƃ��B�����琶���Ă���ȏ�́A�l�����Ӌ`���炵�߂����B�܂������Ă��l�Ԃd���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ�тƂł���A�l�Ԃ��l�Ԃ̑������������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł���B
�@���������ɂ��錳���S�@�֎m�������h�����N���ɍ��R�Ɛ����A���̖���Ɍh�炵�`���V����ꂽ�B�����̂悤�ɔN����������A�������������Ȃ����Ƃ����t���ɓ��@���A���̂܂ܒZ���J���l���̗��j������B��N�ɂȂ��Ă܂��A�l���������̂ŘV����y����łق��������ЂƂł���B���������̂Ȃ��ЂƂ����Ȃ�����������⑧�q����v�w�̔߂��݂͒ɂ����炢�킩��̂ł���B���̂h���̎��͐S�ɂЂ����������B���͂�������Ɖ���Ă��Ԃ߂悤���Ȃ��č������B�V�c�̎��ɂ��Ă͕ʂ̎v�����������B
�@�u���n�ɂ܂��������匳���É��v�ɂ́A�����͂��đ������l�����D���Ă����B�u�匳���v�́u���S�v�������͂��Ȃ̂ɁA���X�͒��P�����R�������B���ځA�����������A�����������肷��킯�ł͂Ȃ����A���̉��̉��̂܂������Ɖ��̒N������u����̖��߂͒��̖��߂��v�Ƃ�����ƒn���ɂł������ނ����̂ł���B
�@�u��Ώ��Ă邩�v�ƔO�������Đ��z���ɂӂ݂������V�c�́A�푈������G�����������ʂ��Ƃ��O���ɂ������Ǝv���B�u�Ⴂ���냈�[���b�p�𗷍s���A��ꎟ��풼��̍r��ʂĂ��Ƃ�����݂Đ푈�͂����Ȃ��Ƃ��������v�ƋL�Ғc�̎���ɓ����Ă���̂�����B
�@���l��N�\�����A�����m�푈�ɓ˓������Ƃ��A�푈�̋]���͉��\���ƌ������A���S���ɐ��������V�c�ɕ������������B����ł����҂̋ꂵ�݂�ނ͍l�������̂ł��낤���B�V�c�̖��ɂ���S�l�\���̏��������ɁA��ЂŎ��\���̍��������B�܂����ɂ��ꂽ�A�W�A���̑��ł͈�疜�ȏオ�E����Ă���B�l�ނ̗��j�ł�����̎S�Ђ������炵���N��͂��Ȃ������Ɨ��j�͍�����B
�@�u�����Ă��邱�Ƃ��߈��Ƃ���Ĕ��F�e���̈Â��J�Ԃ̎�������v�i��Ɨ�ؐ�����̂��Ƃj�ЂƂ���������B���ё����Ɠ����悤�ɁA���x����������A����͎E����A����͂��炭�������̂сA���܁u���a���I������Ƃ����̂ɃX�J�b�Ƃ��Ȃ��ȃ@�v�ƐV���i�u�Ԋ��v�j�Ɉꕶ���Ă����B
�@���܂���V�c�̎��ŗ܂𗬂��A�������f���A�̕����Ȃ���߂āA�r�ɕ����ȂǂƂ������Ƃ���������Ƃ��Ăł�����̂ł��낤���B�u�����v�ł���u�����v�ł���u���ʁv�ł���A�x�z�҂̉��ꂽ���������������߂̑���⓹��ɂ͂̂肽���Ȃ����̂ł���B���̐푈�ŁA�L���A����̐l�����̎c�E�A�ߎS�Ȏ��͒N��ɂ������炳�ꂽ�̂ł��낤���B�܂����{�̓s�s�Ƃ����s�s��j�ł֓��������͉̂��ł������̂��B�q�̓I�ȏ��a���Â���߁A������������ȓ���������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł͂���܂����B
�@�Q �u�쒀�͂̓R���C�v
�@�O���\�O���̏W�c�\�����I���A�ꑧ���Ă���Ƃ���ցu���w�ʐM�v�i�����H�c���A�H����h���s�j�̓�\�l���i��㔪��N�O���j���͂����B�����Ղ̏ڕ�ł���B�����D������Ɩ��S������̒O�����߂������ł���B�ӂ���Ƃ������Ղ͂��ꂼ���ڂ������A�Z���������̂Ɏ��ɂ悭�܂Ƃ߂Ă���A�L�^�Ƃ��Ă������Ƃ��Ă���ꋉ�̍D���œ�ǎO�ǂ����B
�@���Ƃ��̑����Ղ́A�L�O�u�����D�]�������E���r�Y���A�����u�����E�����v�Łu�����E�S���q�܁v�̎�܂����\�����Ƃ����A���ꂵ���^�C�~���O�������B
�@�����Ղ��I����Ă���L�u�ōu�t���͂�Ŕ��ȉ�������Ȃ����B���Ƃ������ł͂Ȃ������������o�āA�a�ꂳ��̖��k�I���ȏЉ�Ŕ����Ȃ���e���v���������ɂ���ׂ��Ă���Ƃ���ցu�쒀�͂��R���C�v�Ƃ��������ˑR�A���̎��������B���Ԃ�A�����̍�i����u�I�H�D�v�Ɉڂ������̂��A���ӂ̐����������B���Ƃ̂͂��ޗ]�n�͂Ȃ��A�g���k�܂��āA���͎����X�����̂ł������B
�N��̃��N�G�X�g���m��Ȃ����u�T�[�J�X�̉S�v�����W�I���痬�ꂽ�吳�Ղ̔��t�ő吳���}�����������Ă鈣�D�̂����ł���B���͂��̉̂ɂ͓��ʂ̏�����B���̉̂��Đ��\�ɂ͈������T�[�J�X�̏������C���[�W����̂łȂ��A����͂��܂���������쒀�͏�������A�z����̂ł���B
�@���͒����[�ׂ͖閶
�@�������Ⴂ���Ȃ��N�����I�l�b�g
�@���ꗬ��镂�_�̉�
�@�������炫�܂��傠�̒���
�@�쒀�́u�����v���u�[���v���Ƃ��Ɏ��́A�X��U���Č����茩����ꂽ���ł���B�Ƃ��Ɂu�A�T�M���v�̐������Ƃ͂��Ƃ����킵�����Ƃ�����B
�@�t�u�L�^�ɂ́A���t��̖��̖��̂����쒀�͂��l�ǂ������B���͂̂ق��́u�V���v�Ɓu�����v�������B����������a�����̌����Ő�Z�S�g�����̈ꓙ�쒀�́B�O���m�b�g�B���^�ł����������̎p�͏d���ŌÕ��m�I�A�����^�������B
�u�A�T�M���v�͈��l��N�����K�_���J�i���̐퓬�ŋ}�~�������@�\���@�̏P���������Ē��v�����B�u���t�M���v�͂��̂Ƃ����v���Ȃ����������j�����B���肩��X�R�[���̂Ȃ��ɓ������ݒnj����܂ʂ��ꂽ�̂ł���B�������A���l�O�N�\�ꌎ�吼[�m]�m�Ő퓬�ɔj���j���狎���Ă������B���͂Ƃ����̍Ō�̎p���g���b�N���̊�n�Ŏ��͌����̂ł���B
�@���{�̓��V���g���R�k���̐���ŋ쒀�͂̌����ɏd�S�������J�펞�ɂ̓h�C�c������ۗL���������B
�@�����s�E����A���{�͍��ۘA����E�ށA�C�R�͑����ɔ��Ԃ�������̂ł���B
�@���l��N����l�ܔN�܂ł̎O�N���J���̂������Ɉꓙ�쒀�͈�Z��ǒ��A�����c��͂킸���O�\���ǁA�쒀�͎͂O��ǒ��A�\�ǂ݂̂Ƃ�����œI�ȑ��Q���������B���ɕ����������ӂ��Ƃ��Ƃ����C��[�����Ȃ������Ƃ͓��R�Ƃ͂����A�����킵��������A�Ƃ��ɂ��̏������e�ɂ��������͂���Ƃ��܂�ɂ��߂����B�����܂��������̈⍜�͂����炭�����ȏ�͐��������ɂ����͂ɂ��܂�������āA�͂邩�Ȍ̍����Â�ł���ɂ������Ȃ��B
�@�u�T�[�J�X�̉S�v�̎��́u���̂���҂����Ȃ����v�Ɏn�܂�̂����A���͑ւ��S�������ĉ̂������̂��B
�@���͒����[�ׂ͗[���^�������Ⴂ���Ȃ��͑��Ζ��^���ꗬ�����̉Ԃ́^�������炫�܂���U��܂���v�B�������Ȃ��炢�܂��A���͒��ɂɂȂ�B
�@�����ǂ�邩�͂�Ȃ����̏d�����̒���ꂽ�C��ɁA�������炾����������쒀�́B����Ɋ͑̂������ɂ��Ȃ���A�₪�āu�����N���v�̓J�B���肩�炳�߂Ē��̉ۋƁB
�@�u�R�͊��f�g�v�ł͂��܂�j�����̈���B�ЂƂ��яo������ƊC�̐땺�Ƃ��ĂȂ�ӂ肩�܂킸�C���삯�ʂ���B����Ƃ��͋����͂̂��邢�͗A���D�̌쑗�ɂ�����B��
�ȋ]���I�ɑ|�C��~���̔C���ɂ����B�I�g���ɂȂ�Ƃ������Ă���B���Ăт�������ł��ǂ��ւł��g���Ђ邪�����ċ}�s����B����͍��ϕ��𒅂��J���҂̂悤�ɋC�y�邾�����B���Օi�������B�������ڂ�̎��Ȃǂ���g�ނɂ͊��D�̂ӂ˂�������������Ȃ��B
�@�o���̂����ɂ����ĊC�R�����̃o�b�^�[��s���^���������B���ꂾ���Ɂu�������Ⴂ���Ȃ��͑��Ζ��v�������B�������Ƃ��킸�A�C�����s�ɐg������A�C�̂����Ə����Ă������Ԃ����B���̕��m�̐S��ɂ���������ƁA��������ɑ���̂ƂȂ�B
�@�푈�̖��c��͊m���ɏ����Ă����B���܁u���a�v���I������B�����A���͂����܂ł������B���ǂ��������Ă�����葱���B�����c�������̂͂�����A�j�V�r�ȁA�傻�ꂽ�o�������A���̌����i���Ђ�����A���܂���̂�����B
�@�u�쒀�́v�Ƃ����c�Ƃɂ�����鎄�̐S�͂������ア����Ȃ̂��A�Ɓu�I�H�D�v��ǂނƂ��A�����������B���łɏ��ё����͈����N�ɓ����̂׃X�g�Z���[�A�v�����^���A���w�̕s�ł̍�i�u�I�H�D�v�œV�c�̊C�R���ے��I�ɂ������Ă���̂��B����̓����S���܂���Ɋ������Ƃ��̂悤�ɖ����ł���B���Ƃ��ƎЉ��`�̌R���Ƃ������u�l���́i���߂́j�R���v�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂��B�����ꂽ�����̍˔\�͂�������j���V�c�̊C�R���X�b�p�����B
�@�u�I�H�D�v�̃N���C�}�b�N�X�B�k�m�ɉ�����H�D�J���ҁB���ʂƈ����w�̓{��B�X�g���C�L�ƂȂ�A�c�̌����n�܂��ʁB�ḗu�������A������Ȃ��ȁv�u�F�悢�Ԏ������Ă�邩��v�ƂӂĂ������B�u�ʼnY�v�͂��������ē̃s�X�g�������������Ƃ��B�u�h��v�͂����������Ȃ���ɑ������炤�B���|���ɂȂ�ēB�e�[�u�����u�l�{������ɂ��āv�Ђ�����Ԃ�B�u�F�悢�Ԏ�?���̖�Y�A�ӂ�����ȁI�������Ă̖��Ȃv�Ɓu�ʼnY�v�B
�@�쒀�͂��߂Â��B�u���܂����v�Ɗw�����͂ˏ��B�u�鍑�R�͖��v�Ƌ��ԘJ���ҁB�i���m�ɂ͋쒀�͂́u�R�́v�ƌĂȂ������j
�@�쒀�͂���O�ǂ̃J�b�^�[���������Ă���B�t�������������m���^���b�v�i�{���́u���b�v�v�ƂȂ��Ă���j������ė��āu�C���D�ɂł��x�肱�ނ悤�ɂ��āv�X�g���C�L�̋��v�␅�A�Εv����͂ށB�u���܂����A�{���v�u���Ⴊ�����ȁv�Ɓu�ʼnY�v�����B�ΏƓI�Ɂu���܌��₪��v�Ƃ����ēB�X�g���C�L�ɓ����Ă���̊ē̕s�v�c�ȗ��������A���̂Ƃ��킩���@���\�\�B
�@�L���́u���a�L�O�����فv�ւ������ЂƂȂ番�邪�A�����ʂɍ��X�Ƒ�p�l�����W������Ă���B���͂��̑�p�l���������Ƃ��A���炾�������Ă��܂����B���̑�p�l����B29�B�e�̌�����������̈��L���ʐ^�ŁA�L�����ɍL�����L�m�R�_�ƍ����Ɍ��������ꂷ��s�X�A�����Đ��˓��̓��X���ʂ��Ă���B���̔\�����̐��݂�����ɏ����Ȋ͉e�������̂��B�����ڂ��̂���}�X�g�B�d�g�T�m�@����t����ꂽ�O���}�X�g�Ɠ����̂���͋��B����͂܂������Ȃ����̏�͂������쒀�͂Ȃ̂��B���ăG�m���E�Q�C���}�������A���������ƃJ�^�L��łƐ������t�̎c�����A�͂邩�Z�烁�[�g�����̉��̊C�ŃL�m�R�_�����グ�Ă���̂������B���́u�����v�Ɛ����̂݁A���̏�ōd�����Ă��܂��B�₪�ĔM���܂Ŗڂ��ӂ����ł����B�݂��ڂ炵���p�ŁA���Ȃ��̐e���Əo����Ȃ悤�ɁA���������Ă��܂����̂ł������B�i�u�H�c���啶�w�v14���A1989�E6�j
|
||||
|
||||
| 4 ���s���ΊC�̉��́i�Q�j | ||||
|---|---|---|---|---|
�@�@���A�u���a�v�̃t�B�i�[����
�@�\�r�q�ł�
�@���������ς��ɂ����V�C�̖��}���Ђ낰�Ă���B����ꂽ�和�������A�S�̔��̓����͐Βi���B�_�C�_�C�̖�h�S�₵���Ȃǂ̒g�ѐA�����������ĉ��i������Ɨm�ٕ��̉Ƃ�����B����ȉƂ����グ�鍂���܂łɌ����Ȃ�ԁB�r�q�̐X�͂Ƃ݂�Ɨ͓��ɋP���A���ɂ��悢�ł����B
�@�|�J�|�J�z�C�ɗU���Đ_�����w�ɉ��肽�B�r�q�̒��̕��֕���i�߂�ƁA���������傤����ȏ�����܂肵���Ƃ�Âт����ƕ��̉Ƃ������B
�@��㔪���N�܌��B�A�x�������Đ��q�̒����ЂƂƂ��Î�Ȃ��̂ɂ��Ă����B���������q�s�̒r�q�Ԋ҉^���͌���ȍU�h�̂����ɂ������B���N�̏\���A�u�r�q�ɕČR�Z��͌��Ă����Ȃ��v�Ƃ������E�x��s���̕����������̂����A��N��̏\���ɂ́A�܂��s���I�����˂Ȃ�Ȃ��B�x��w�c�ɂ��Ă݂�Όܓx���u�ČR�Z��m�[�v�̐R�����������Ă���̂��B������ŃA�����J�����{���{���f�O����̂�������܂��Ȃ̂����A����ɗ������Ȃ��B�e�F�h�͐�p��ς��A�r�q���𑈓_���炻�炻���Ƃ��A�Z�a�����ł��o���͂��߂��B�����炵���U���ł���B���܂�x��s���������u�Δh�v�͕w�l�𒆐S�ɂ����s���O���[�v�Ɛ��}�ł͋��Y�}�����Ȃ̂��B�����A���Ђ��e�F�h�A�Ȃ����Љ�A���������哊�[�Ƃ����B���ʂƂ��ėΔh�ɗ����ӂ�����ԓx���B
�@���q�s�V�h�ɏZ�ގႢ��w�����Ń��j�[�N�ȐV���u�ł��E���炵�v�����s����Ă���B�i���q�s�V�h�O�\�܁\��F�J���j�n���͈�㔪���N�\�B�n��ɂ͂��߂Ẵ~�j�R�~�������A�Ȍ�A����������Ă���B����̕�炵�𒆐S�ɁA�s���̖ڂɂ��������̖��_����w�̗��ꂩ����グ�A�^��_���w�E���A�����Ȃ����̂͂����Ȃ��Ƃ����������̂���ҏW�ŋ������ĂԁB�a5���E���y�[�W���āB��畔���Œ����ɔz�t����B�����͔��l�̕ҏW�X�^�b�t�̎������݁A�J���p�B���ꂩ�琀�q�C�݂𐴑|���ăA���~�ʂ��W�߂�B�Ȃ�Ƃ����̃A�}�`���A���Y�����A�}�`���A�����Ƃ̕x��s�����x���Ă��銴�����B�����Ă݂�Έ�˒[��c���ڂ̏�Ȃ̂��B
�@���́u���̐V���v�̒��S�ɂȂ��Ă���F�J����q����͎O�\���B�u�V������낤���Ă������������ǁA�����ĉ��������m��Ȃ������B�ł��݂�Ȃł��ł�����̂Ȃ̂˂��B�v
�@��㔪�Z�N�\��\�������̒����V���u���v���ł͎��͂��̌F�J����q����̓��������ăt�@�C�������B���̈ꕔ�͎��̒ʂ�ł���B
�@�u�r�q�̐X�����āv�i���q�s�F�J����q�E��w�O�\�܍j
�@�r�q�ČR�Z����ɂ��Ē��F�_�ސ쌧�m���͂��̂قǁu�����P��͍���v�Ƃ��������������B����܂Œ��F����́A�n���Z���̈ӎu�d����Əq�ׂė������A�x��s���a���̎��ɂ́u����͐��q�s�Ƒ����݂����낦�A���ɑ����ݔ��������Ă����v�Ɩ��������ł͂Ȃ����B���N�̒m���I�������I���ƂȂ�̂��m��I�ƂȂ�₢�Ȃ�́A���̔����ł���B
�@�ČR�Z����Ȃ��r�q�Ɍ��Ă˂Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ����A�ł���{�I�őf�p�Ȗ₢�ɂ܂Ƃ��ɓ����Ȃ��܂܁A�r�q�ɌŎ����鍑�������̂́A�������ɂƂĂ�������낤�B
�@�������A���̍���ɂ��˂苭���O�x�̃��R�[���A��x�̑I���ƘA�q�s���������������Ă������̂́A�����̂ɂ��ウ��r�q�̐X����邽�߁A�������ꂾ���������B��s���B��̎��R�̐���͍����̕�ł���A�������q�s�����̂��̂ł͂Ȃ��B�i�㗪�j
�@�����ȗE�C���锭���Ƃ����ׂ��ł���B�Δh�ɂ͌F�J�����̂悤�Ȍ��I�A���R�l�I���z�̐l�����������ɂ��Ă���̂��B�r�q�e��ɂ̐X�͏������̌ܔ{������B���̘Z���̈��ČR�Z��ɂ��Ă�Ƃ������A�������͑S�̂̎l���̈ꂪ�g���Ă��܂��̂ł���B
�@�u�ł��E���炵�v�̒��ő��ꐴ�q�������u���q�̎s���̊Ԃɉ萶��������̖����`�B���̑o�t�𗧌͂ꂳ���Ȃ����߂ɂ́A�ЂƂ�ЂƂ肪���X�ӎ����s�ɂ��A�E�C�������čs�����Ȃ���v�Ƒi���Ă���B
�@���q�̍��l�͔������B��O�͑��������B�Â��ȗ̒����B���鎩�R�����w�������u�r�q�̐X���Ȃ���Ȃ̂��B���̐X�̈�{��{���玄�����͂Ђƌ��̑������炢�������Ă�����Ă��܂��B�X�͒n���̏�ł���B�r�q�̐X�����킹�Α��͘p�̐����悲��܂��B�����̎q�ǂ��̂悤�ɒr�q�̖X�Ɉ�{��{�A���O�����đ�ɂ��悤�ł͂���܂��v�Ə����B
�@�����͂̂�����������́u�ӂ邳�Ƃ̐X�Ƃ܂��̐����v�̂��߂ɂ݂�ȂŐ���Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�@�F�J����̎莆�B�u�����Ȓr�q�̐X��ʂ��ĂЂ낢���E�������ė��܂����B���������̃X�L�����_���ɂ���Ă�������A�s�����������߂ɒr�q�̖�ȂLj��͂͂͂��������̂�����܂��B�ł��A�������͂��̓{�����{�̖����`�̂��߂ɁA�܂����������l�Ԃ炵�������铖�R�̌����̂��߂ɁA�݂�Ȋ�F��ς��Ĕ�т܂���Ă���̂ł��v�B
�@�u���a�v�̃t�B�i�[�����͂��܂����B�u���a�v�͏����K���ɂƂ��āA�炭�Ȃ������B���́u���a�v�̂������ɂ��߂Đl�Ԃ炵�������Ă������]�������������B���ꂪ�L�I�̔��Ƃ������̂ł���B�u�v�V�v��u��}�v�Ƃ���ꂽ���͂������Ɏp����ς��A���v�V�̑��ɑg���Ă����͎̂c�O�Ȃ��Ƃ��B�����Ɂu���핽�a�v�𐺍��ɏ����悤�Ƃ����q�̂��������̂悤�Ȑ��������A�\�������A�G���������Ƃ�������I�ȂƂ��ɖ��X���X�ƂȂ�B
�@�r�q�̓y������ɁA���X�ɁA���܂�|�̃c�������Ă��悤�Ƃ��Ă���̂������B�X�̎��͓͂S��Ԃƌ����R���N���[�g�����͂�ł��ė]�l���߂����Ȃ��B�����߂����Q�[�g������B
�@�u�ݓ��ČR�{�݂ɂ���������ւ��B���Ȃ�������͓��{���@�߂ɂ�蔱������v�Ƃ���̂ł���B�ČR�Ɠ��{�̃K�[�h�}�����Q�[�g�ɂ͂������Ă����B
�@�u�r�q�̌����Ə����i�ρv�Ȃ���̂��������B�u�ĊC�R���{���n�i�ߊ��v�Ɓu���l�h�q�{�ǒ��v�̖����������B�t�R���R�c�n�̖k������̌i�ςƂ��Ă��邪�A�����ɂ��L���r�q�̐X�ɂƂ��āu�ČR�Z��͂ق�̈ꕔ�v�Ƃ�������̊G�ł���B�����悭����ƐX�ɋ���ȃr�����������������сA�A���e�i�̓S����e�j�X�R�[�g��^����炵���n�ʂ��\�ɂƂ��A���̖ʐς͈�̒c�n�A��̒��ǂ���łȂ��̂��B
�@���łɐ��q�s�̔�����������A�ČR�Z��ݎ��Ƃ̖{�i���H�̑O��Ƃ����ׂ��r�q��̕t���ւ��Ɩh�В����r�Ȃǂ̍H�����D�����s����Ă����B���{�͒r�q�̐X�ɂȂɂ��Ȃ�ł��u���h�[�U����ꂽ���̂��B
�@���q�X���߂��ɏ��������������B���͏���ׂ��Ђ炭�ɂ͏����������A�؉A�̂׃��`������ђ��т��قق����B���Q�̒������܂������B������A���N����w�l���ʂ�A
�@�u�����A���̂ЂƂ������A�����J�Ɠ��{���{���ނ����ɂ܂킵�Z�N�Ԃ����������ĕ����Ȃ��ł���ЂƂ��v�Ƃ������B
�@�����Ă͊C�R�Ɏ��R�ɂ��ꂽ���̐X���A����ǂ̓A�����J�̎��R�ɂ����Ȃ�āB�u���q�s���悪����āv�B���ׂ͂̃g���̑����������Ėڂ���グ��B�q�A��̎Ⴂ���ꂳ�u�L���b�v�Ƃ�������̎����������Ă����������B
�@�u�q�g���[�͐l�ԂȂ炸�Ƃ������c��̕ꍑ�h�C�c�Ɉ┯�������v�i���q�s�E��ؗ��b�q�j�B���͐��q�s�̃G���K���g�ȁH�w�l���V���̉̒d�ɂ̂����̂��v�������A�����̂�������X�����グ���̂ł���B
�@�\���{��ł�
�@���{����͎��ɂƂ��ăZ���`�����^���S�����B���{����ɏ��Ə��N�̂悤�ɋ����Ƃ��߂��B�����͉�������ł��Ȃ����A���{����͎��̐t�ւ��ǂ铹�������B���q���������q�ɂ���������ƃh�L�h�L���Ȃ��炠����̕��i�ɖڂ����͂�B�c�Y�≡�{�ꂪ�߂����ɂꎄ�͐g����肾���`�̔g�ʂɖڂ����Ȃ���A�S�͊C�ɑ����o�Ă���B
�@���l���m�́u������A���ė��ĉ��{��̋�C���z���Ƃق��Ƃ���B�ӂ��ƌ������ďo��Ƃ茾�����{��ق������肷��v�Ə����Ă���B
�@���̓������͒��������{����ɔ�т̂����B�a���≮�ł̎d���͂��܂������O���̂����ɂ��B���{��s���̖ړI�́u�����̗V�сv�������B�V�����ł����O�}�����Ƒ���u�O�}�����܂�v�ɂ������B
�@����ł����͉��l�ŋ��}���ɏ�肩���r�q�Ɋ�蓹�����B�r�q�̐X���������茩�Ă��������������ƂƁA�r�q�̐X����鐀�q�̂��������������܂݂����U�f�ɂ���ꂽ�̂ł���B
�@�����牡�{��ɂ����Ƃ��́A���͂���������āA�`���U������ЂƂ̍����V���G�b�g�ɔg�̌��肪�͂˕Ԃ��Ă���B�C�ɓ��e���铔��͉����Ă����B�h�̈ꍑ���ɂ��Ƃ��������͉��ɂނ������B
�@�Ⴋ���͂▲�Ƃ���
�@�킪�F�݂Ȑ��������
�@���̐��Ɋy��������
�@�������ɂ����Ă�
�@�I�[���h�E�u���b�N�E�W���[
�@�����s���ނ͂�V�������
�@�������ɂ����Ă�
�@�I�[���h�E�u���b�N�E�W���[
�@�Â����݂Ȃ���t�H�X�^�[�̉̂��������ށB�ꍑ���̂��鎬�������獑���\�Z�����Y���ɂ��邫�A�ՊC�����Ɏ���A�{���A������s���B�u�������ɂ����Ăԁv�Ƃ����������������B���͌�肠����ǂ���F�����X�Ɏ����ė����B�ŋ߂����̂ЂƂ�����̐��֑������B�u�y���������Ă���v���ǂ����킩��Ȃ����u�Ⴋ���v���͂₷���������Ƃ������������ɂ������B
�@�u�Ⴋ���v���v���ĉ��{��w���ĕςڂ����鉡�{��ɂ͗��_���邱�Ƃ������B�h�u�ʂ�̃u���u���������A�����J�F���Z���ď�Ȃ��C�����ɂȂ�B�x�[�X�q�A�����J�C�R��n�j�̑O��ʂ�Ƃ��́u�����Ȃ��v�v���ɂ�����B�ՊC�����ɂ��܂��팩�傪����A�C��Ζ�����ɏ㗤����Ƃ����̖��ʂ�A���Y�⎬���ւ��肾�������Ƃ��v����������B�������A�������猩���鉡�{��`�ɂ͐����͂�쒀�͂⏄�m�͂����܂��ɕ�����ł���B������肩�A��O�̎E�Ƃ������C�Ƃ܂ł͂����Ȃ��ɂ��Ă��A���邽�тɂ��̐��͂ӂ��Ă���̂ɂ͗J�D�����ڂ����B
�@���̉��{��ɖ������̂��L�����̂ɂ͂��悢�戠�R�Ƃ�����ꂽ�B����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂������B���{��̐V��������O�}�����̎O�}�͑O�L��ɓ������t�̓����������Ă����̂��B
�@���R�Ƃ����v���ŏh�ɋA�������́A�������ܒn�����̐_�ސ�V���ɓ������������B�n�K�L�ɂ��܂������ŏ������B����͌܌��\������̓����u���R�̐��v�Ɏ�肠����ꂽ�̂ł���B
�@����́u���{��ɕ��a�w�ׂ�{�݂��v�̌��o���ł���B���͉����̌����J���A���̈������ɂ��Ă��ʂɈꖇ���������A����͎�肠�����Ȃ������悤���B�����͂��܂͖��l���ł��邪�A�����̂ނ�������v�ǂł��������Ƃ͒m����B���܂͎��R�L���ȍs�y�n�����A�r��邪�܂܁B���R�͕��u���Ă͎��Ȃ��Ƃ����咣�������B
�@���{��ɕ��a�w�ׂ�{�݂��B�v���Ԃ�ɉ��{���K�ꂽ�B���܂��܌��Ⴆ����ɔ������Ȃ����O�}�����́u����O�}�����܂�v�Ɓu�h�u�C�^�E�o�U�[���v�̍ŏI���ɑ������A����_�ɂ��ĕ������B
�@�u�܂�v�̕��͉��R�s���̂������ɂ��Ǝl���ԂŘZ���l�������Ƃ����B�Ԃ��萅���艉�t����A���܂��ɐ���̏��Ă��ނ�����ɂӂ��킵�����C�x���g�ł������B�镗�ɂ�����Ȃ���W���Y���t�ɍ��킹�郌�[�U�[�����╬���V���[�Ɏ��̂��̂�Y�ꂽ�B�������A�r���������s��D�i���ʂ�������Ȃ������B
�@���̓_���X�z�[����X�g�����ɂ܂Łu�������v�O�}�͂��A�K��邽�тɕ⋭����A�C������A���܂�Е����X�̎p�ɐ��܂�ς�A�ό����{��̖ڋʂ̈�ƂȂ����B���܂����O�̕x�������̎v�z�𐁂����ނ��߂ȂǂƂ͒N����M���܂��B�������A�͂̑O��Ɂu���������v�̓����܂ł����o�܂��ɂȂ��Ă����̂ɂ͈��R�Ƃ�����ꂽ�B
�@���a���肤�����̈�l�Ƃ��āA�܂����C�R�̐l�ԂƂ��Ă��̓����͕s������������B����łȂ��Ƃ����{��s���͊j�𓋍ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^����Đ����́A�q���͂̓��`�ɂ��炾�����ւ����Ȃ����B���{��͍L���Ɋw��Łu�푈���j�����فv�̂悤�Ȃ��̂������ĕ��a�ւ̎v�������߂�ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�s���̈�l���肤���̂ł���B
�@�ȏオ�u���R�̐��v�ɂ̂����S���ł���B��㐔�N���ĎO�}�͂̌����J���L�u����J�p�̗v�����������B��F�ɋ`�����Ă��ĕn�҂̈ꓔ�𓊂������ł��邪�A�N��ł���A���̃J���p�͕��a������ނ����A�s��𐾂��Ă̎O�}�֑͂�����������͂��ł���B
�@�u���������v�͂������ɓ��I�푈�̖�����������{�C�C��̑叟���̒�ł͂���B�����R����`����𐴎Z���������`�ږ{�ł͎O�}�͑O�œ����ɂ܂łȂ��ċ��D���������Ƃ͂Ȃ��̂��B���E�ɗ�̂Ȃ��C�R�̃o�b�^�[�i���فj�͓����̔������ƒN���������Ă��������A���̐��_�_�����Ƃ������ɍV�����l�Ԃ��ς�B����鑤�̐Ӌ�͑S���S�[��ȊO�̉����ł��Ȃ������͂��Ȃ̂ɁB
�@�\����̐_�ސ�V���̎��̓����ƊW�͂Ȃ��������A���R�A�܌��\�����̒����V�������������̎ʐ^����ʂɌf���A���w�Z�Љ�ȂŁu���j��̐l���v�Ƃ��ē�����������Ƃ��������Ȃ̌v����X�b�p�������B��������u�Ԋ��v���͂��ߊe���͓��������Y�Ȃ�u���j��̐l���v�����������ɏ����͂��߂��B
�@�܌���\�O�ځA�_�ސ�V���͈�ʃR�����u�Ɩ����v�ɓ��������ᔻ���f�����B�v��Ǝ��̒ʂ�ł���B
�@���C�R�ɂ����H�c�̐l���v���Ԃ�ɉ��{���K�ꂽ���z���A�悲��{���́u���R�̐��v�ɊĂ����B�u���̓_���X�z�[����X�g�����ɂ܂Ň����������O�}�͂��K��邽�тɕ⋭����A�C������A���܂�Е����X�̎p�ɐ��܂�ς�c�c�͂̑O��ɓ������t�̓����܂ł��o�܂��ɂȂ��Ă���̂ɂ͂��������т����肵���v�Ƃ���B���������Ƃ����A���w�Z�̊w�K�w���v�̂̌�������i�߂镶���Ȃ��A�Z�N���̓��{�j�w�K�Ɂu�K����������j��̐l���v�\�l�̒��ɋ����Ă���i�u�����v�j�Ƃ����B�܂�����ł͂Ȃ����������铌������I�ł���B���{�C�C��͌܌���\�����i���C�R�L�O���j�B�Ɩ����q�͋��N�̍�����u�V�͂̐Î�ȗ]���ɂ������̂ł́v�Ə��������A�j���ڊ͂Ƌ^����ČR�͂̏o���`��������ŁA����ɕs����������H�c�̓��e�҂́u���{��͍L���Ɋw��Ő푈�j�����فv�̂悤�Ȃ��̂������ĕ��a�ւ̎v�������߂�ׂ��ł͂Ȃ��낤���v�ƌ���ł���B���j�̎�������������A�䂪�߂��肷�邱�Ƃ̌��͎w�E����܂ł��Ȃ��B���씭���ł͂Ȃ����A���̎������ǂ��]�����Č�܂�Ȃ��㐢�ɐ������Ă䂭���ł���B��ÁA�q�ϓI�ȗ��j�ς�����B
�@�����ǂ�Ŏ��̓}�X�R�~�̂Ȃ��ɂ��A�܂����a�̖��𐽎��ɍl����L�҂̂��邱�Ƃɖ��������B�V�������_���Ƃ肠���A���_���V���𖡕��ɂ��Ȃ���A����a�̕����ɋO���C�������Ă����Ƃ�����̕��@�_���w�C�����������B�������͈�J���ȏ���e�����X���������A�]�C�͐��J�������Ȃ��s�A�����������ܗ����Ђт������B
�@���m�u�T�C�p���ƌĂꂽ�j�v�͐�O���̉��{����A�v�����݂����Ղ�ɂ������Ă���B�ČR�i���̕`�ʂ����͂������B����ɂ��Ɣ����O�\���A�R�`���̊͒��Q���琯������g���ď㗤�p�M�����㗤�����̂ł������B���S�������������̂��Ă��������ɔ��i���e�V���������������B���̎��A���{��̓��{�C�R���͂͏\���Z��ł������Ƃ�������A�ČR�̕������Ȃ�ْ����Ă����̂ł��낤���B
�@���̔������B��̑���������u�s�ˎ��v�����X�ƋN�����B�O���Ȃ���h������Ă�������A���W�̎�L�����p����Ă��邪�A����͋����A����A���q�f�v�A�\�s�A���D�A���D�f�v�A�\�߁A�x�@���ɑ���s�@�s�ׁA�Ƒ�N���A�j��ȂǂȂǁA����͂����A�����ւ�Ȃ��̂������悤���B���҂̂�����s�҂̋��J�A���{��s���͂���ɍR���ς����̂ł���B
�@�����ɊϔO���̖������̂��Ƃ������Ă���̂łȂ������ǂB�u�������v�Ƃ����͔̂��t�h�̂��ƂȂ̂��B�\�Ŕ͎��������A�ϔO�����ӂɂ͎O�S��������A�ꌬ�Ɏl�A�ܐl�̏������Ēj�̑�������Ă����̂ł���B�j�͊C�R���H�Ђ̍H���Ȃ̂��B�u�������̊Ԍ��͂ǂ��������A��Ԕ������x�������̂ł͂Ȃ��낤���B����ɂ�������m�����̌��������Ɉ�Ԃ̈����˂��傫�������J���Ă���v�Ƃ���A�����ȕ����Ɉ�������ő�������邩�킢�����ȏ��������ق��ӂƂ�����B���{��ɂ͂ق��ɔ��ؓc�ɗV�f���������B�u���W�͏H�c�A�E�X�A�R�`�c�c����Ȃǂ̔_�Ƃ̖������������v�Ə����Ă����B�����̏��͌ܔN�œ�S�~�̔N������������Ƃ����B���l���m�͉��{��́u�ØV�����ӂ邳�Ƃ̗��j�v����E�������������A��O�A�����肾�Ƃ����H���j���Ƃ����̔ߎS�Șb�ƂȂ�ƂȂ�����ԂɏH�c����������B���܂��ɑS���B��̐l���������ł���A�n�����i���o�[�E�����̒n�ʂɊÂĂ���̂ɂ͂ǂ�ȗ��R������̂��낤�B�H�c�̐l�Ԃ͂������Ă݂�Ɛl���ꂼ��L���b�ƌ�����̂����Ă���̂ɁA��������Ȃ��ł���̂ł��낤���B�n�����ł��A���m�ł��Ȃ��Ƃ����C������̂����B�i�u�H�c���啶�w�v13���A1989�E1�j
|
||||
|
||||
| 5 ���s���ΊC�̉��́i�P�j | ||||
|---|---|---|---|---|
�@�@�Z�A����������ė���
�@�f��u�Ԃ����ԁv�i�W�����E�q���[�X�g���ēj�Ń��[�g���b�N���u�Z���r�A�������A�ނ����Ăނ����͗r�����ɂ����Ȃ������v�Ƃ�����ʂ��������B�����X�J�b�Ƃ������A���������l�����̂ł��鐼�m�̐l�ԂɊ��S�����B���[���b�p�͓��{�̂悤�ɌÑ�̗��j�������܂��łȂ�����A�����`�Ƃ����Ƃ��������K�͂��A�����ĎЉ�ɂ��l�Ԃɂ����݂Ƃ����Ă���B������v���o�������̂��u�S�����_�����v�Ȃ���̂������B
�@��㔪���N�\�\������A���킽�������t���̉w�Ŕ������u�͖k�v�̈�ʁi���������������j�ɂ��ꂪ�̂��Ă����B�L���͗\�����Ă������̂̎������]�������B
�@�L���ɂ��Όܐl�̂����l�l�܂ł��A���܂��Ɂu�����v�������������悢�Ɠ����Ă���̂��B�u�V�c���v�ɂ��Ă͔��O�p�[�Z���g�����܂̂܂܂ł悢�Ɛ��F���Ă���B�u���ۊ��o�v�Ƃ��u�S�n���I�v�Ƃ��Ƃ������Ƃ̍D���ȓ��{�l�ɂ��ẮA�Ȃ��Ȃ���������Ȃ�������݂̂悤�ł���B���܂����āu���a�v�ȂǂƂ������E�ɒʗp���Ȃ������łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����M�O�̌ł��ł��낤�B����Ƃ����m�̌̂ł��낤���B�u�V�c�ے��v���蒅���Ă����݂̓V�c�̈ʒu�Â��ɂ́u����Ƃ������Ȃ��v���l�Z�p�[�Z���g�A�u�S���Ȃ��v��������ƌv�Z�܃p�[�Z���g�ł���B�V�c���܂����A�ɗz�ɕ\�̕���ɗ����Ă��鎞�i�w�f�[�������Ȃ��j�A���S�A���ᔻ�ł���Ƃ������Ƃ́A���{�l�̐��_�̖����n�������̂łȂ����B
�@�V�c�́u�푈�ӔC�v�ɂ��Ắu����v����܃p�[�Z���g�u�Ȃ��v����l�p�[�Z���g�B�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v���l��p�[�Z���g������B�啔���̐l�͐��_�����Ȃ�ė���ꂽ�o���͂Ȃ��ɂ������Ȃ��B�����Ă������̈ӌ����ɏq�ׂ�Ƃ����̂͋��Ȃ̂��B������u�Ȃ�Ƃ������Ȃ��v�Ƃ����B���͂���͈Ӗ����[���̂ł��邪�A�̐����͂�����t��ɂƂ�ő���Ɉ��p����B�u�Ȃ�Ƃ������Ȃ��v�͂����ɖ��ӔC�ł���A�G�S�C�Y���ł��邩��m��ׂ��ł���B
�@����ɂ��Ă��u�V�c�v�s�p�̎v�z�́A��r�Ɂu�V�c�v�̂��߁u���Ƃ̂��߁v�Ђ�����u�Ŏ�����v�������̂悤�ȁA���m�Ȑ푈�̌��҂̎����ɂ����Ȃ��̂ł��낤���B
�@�u�g���낪���w���̊ہx��������Z��̓��\�]���ƂȂ�Ȃ���v�i�c���q�j�B���t�����̓����Ɠw�͂ɂ�������炸�u�N����v�Ɓu���̊ہv�����猻���W��ɓD�C�ł����肱��ł���B�푈�͍��������������A�ӎv���n�b�L�������Ēc�����Ă�����A�����ɌR����`�҂⌛���A�x�@���}�������Ƃ��Ă����s�͕s�\�ł������B�u�푈�ɔ�������A�J�ƌĂ��v�u�s���A�ڋ��҂Ƃ̂̂�����v�B�s������E�C���Ȃ�����ɂ�������������ʂ��A���̏\�ܔN�푈�ł���A���̔s�킾�����B
�@�@�@�u���������v�̑���j
�@�u�E�C���Ȃ��v����Ɏ��͊C�̑����ƂȂ铹��I�l�Ԃł���B�����Ղ��I����Ă���̔��ȉ�ł́A������������Ƃ����̂ɒE�������B�}�l�̔߂����A�ЂƂɌ��Ƃ��Ȃ��z���ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�B���͘b���Ă���Ԗʂ����B
�@��㔪���N��\����A�u���╶�w�[�~�ŔM�ق��ӂ�������|�]�_�Ə��іΕv������˂�����Ċ��t�����B���ꂩ��e�����z���q�ׂ��Ƃ��A���C�������Ă��܂������̂ł���B���т���͑c�ꂳ�H�c�̏o�g�Ƃ����B���̂������H�c�ɂ͓��ʐe���݂������Ă���悤�Ɋ�����ꂽ�B���w�[�~�ł͏�����̂ЂƂ�ЂƂ�ɂ��A������������܂����肵�Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ̂͂��͂��ɂ₳���������ӂ�Ă����B����͖k���̕��y�ɑς���l�Ԃւ̈���⓯�������̂��������B
�@�����I�Ȗ邾�����B���͒��q�ɏ�����B�펞���A�V���Ƀv�����^���A�����܂����̕��������Č��e��������������ƁA���ꂪ�ߏ��̉\���ɂ̂ڂ�A�������������ƁA��[���]�䕚����Ǝ莆�̂��Ƃ肪����A����܂ł����ɘA�ꋎ���邱�Ƃɐ�]�������ƂȂǂ���ׂ��Ă��B
�@�u�Ė[�זE�v�i�v�����^���A���w�S�W�j���o�łɂȂ�������̍�Ɨ�ؐ������u�y���P�̋L�^�v�̒��҉ԉ�����������Ȃ��Ă����B�H�c���啶�w�̎x�����⑽���Ղ̎��s�ψ����̂ق��������������߂Ă����B
�@���l��������ނ���⓯�s�̌��W���[�i���X�g�s���Ƃ͒��������������A����Șb�Ȃǂ������߂����Ȃ������B�u���܂����v�Ǝ��͌�������B���킸�����Ȃł������B�u�����v�ɂ��Ă������b�����A������u�����J�v�̈䕚����ł��A���̏�ʂɏo���͓̂��˂Ȃ̂������B���͐[���p�����B
�@��I���Ǝ��͋}�ɐS���d���Ȃ����B�A���ƒ��S�ň䕚����u���E���y�L�v���Ђ��Ƃ��B�W���X�~���̏����Ȕ����Ԃ��炩���Ă���B�����͏t�߂��������Ă����B
�@�u�i�����P�J�̒ދ�X�v�j���ꂩ�������l�A���ё����̂��Ƃ��������͑傫�Ȑ��Œ���Ɛق������B�����͈����P�J�Ɉڂ��ė���ƁA�s�m�`�I�̏�A�q�̗���M�V�ɘA����āA�ꏏ�ɂ悭���̓X�ɗ����B����͈ȑO���爢���P�J�ɂ�̂ŁA�������͌Â�����m���Ă�B�V�Ă̑����̂��Ƃ͂悭�m��Ȃ����A���̐Â��ʼn��������Ȓj�̂₤�ł������B�������Ȃ𗧂��ė��āA�X�̋��d�l������₤�ɁA������Ƀr�[���𒍂��ł���邱�Ƃ��������B���Ă��ꂾ���Ō����Ă��Ƃ͎v�ւȂ��B�Â߂������ܖڂ̐��������肩�����g�ɂ��Ă�₤���B����S���Ȃ����Ƃ������`�͂������ɁA���͊O���ɂ������ƃs�m�`�I�ɏW�������A�Y�������q�ɉ����ē����ė��Ă��̂��킩�����̂ŁA�������͂��������A���ė����v�B
�@���̍��i���O��A�O�N�j�u�����P�J��v�i�����ɂ́u�����P�J������v�B���l�����̏W�܂�j�̗����ɁA�u�����v�����낿��낵�Ă������Ƃ́u�����v��ǂ�ł���҂ɂ͋����ɂ�����Ȃ��B�������A�ُ�Ȃ��Ƃł������B����̕����́u������l�v�̈�l�Ƃ͉͏㔣�̂��Ƃʼn͏�͈��O�O�N�����̏\���A��������Ă���B�u�ꌎ�O�\���ɂ͓ƈ�̃q�g���[���t�����������B������������J�����������Ă��ƁA�ƈ�̍����𗧂Ă��ƈ��g�����̎ԂɌ����āA�ʂ肷����̓��{���Z������̗��������i�����邱�Ƃ��������v�u�������̔N�A���ё����̌����������V���ɏo�����A���͈����P�J�̃s�m�`�I�ŊO���ɂƉ���ė���M�V�����s����b���ɗ���̂�҂��Ă�v�Ɩ������Ă���B
�@�������܍ΔN���̖���́A���̌�A���O���N�u�W���������Y�Y���L�v�Œ��؏܂��B�l�Z�A�l��N�ɂ����Ď��͈䕚����Ɖ��x���莆�̂��Ƃ肪�������B�����A���쓡��̎�ɂ����u�R���g��y���v��ʂ��Ă������B����ǂ�A���M�����Ẵt�@���̎莆�ɑ��ċV��I�ȕԎ��������Ǝv���B
�@����͎O���N�Ɂu������W�v���A�l��N�Ɂu���H�Ɩ����v�Ƃ������W���o�������A���@�����������ɓ����͂��͂Ȃ��A�V����G���̏��i��ǂ�Ńt�@�����^�[���������̂ł���B
�@�u������W�v�͎O���N�܌���c���[�̊��B�l�Z���ό^�̑ܒԂ̘a�{�ŕS�\���̌��肾�����B���[���A�ƃy�[�\�X�ɖ�������i�Œm���閐���A���̎��҂������I�Œ������炸�A���Ƀ��[���A���������B�m��◛���̊����̖��������͏����Ƃ߂Ă���B�Ȃ�Ƃ����������A�܂��ӂ�������B���̎������Ԃ�u������W�v�̂��̂łȂ��������B
�@�R�m�T�J�d�L����P�e�N��
�@�h�E�]�i�~�i�~�c�K�V�e�I�N��
�@�n�i�j�A���V�m�^�g�G���A���]
�@�u�T���i���v�_�P�K�l���_
�@���A��O�̗����߂Â��Ă����B�u����Ȃ�v�����Ȃ��~�̎��オ�Â�鎍�ł���B�Ō�ɂ���������ւ̃n�K�L�ɂ́u�߂��R�̎w���œ���ɗ��v�Ƃ��������Ƃ����܂����ڂ��Ă���B���N�M�̑����̌܁A�Z�s�����؉H�܂�������������Ă����B
�@���̎l�\���������x�e������Ƃ܂ł����A�R�֎�肾����鎞�オ�������ƂɁA���͈��W�ƂȂ����B�܂��ăI���@�������ՂƂ��Ă��Ă悢�̂��낤���B����A�������Ă����Ȃ��Ƃ����C�����ɂ��������̂ł���B
�@�@�@�u�ԕv�G�L�v�Ă�܂�
�@���l��N�O���\�l���Ə\�ܓ��̓��������V���w�|���ɐٕ����ڂ��Ă���B���D���̗F�l���}���قŌ����Ă���ăR�s�[�������ė����B�l�\�N�����Đ�O�̎��̗B��́u��i�v�Ƒ�������C�����͕��G�������B
�@�����A���łɐV���͎l�y�[�W���ĂɌ��y�[�W���Ă����B�L���������邩��S���X�y�[�X������Ȃ������B���̊W�Ŏ��̒t�قȁu�ԕv�G�L�v�͓���Ԃɂ킽�蕪�ڂ��ꂽ�̂ł��낤�B
�@�{���O���ɔo�l�����ۓ��u���瓤�̖v�������Ă������B�l�\��N�O�ɂ݂����́u���瓤�̖v�ƑΖʂ����b�u���̔o��U���v�E�͎��ɖ����ł܂������I�ł������B�����l�\�N�Ԃ�ɑΖʂ��������̕��͌�������Γ��肽�����̗c�t���������B�����̐V���͑S�\�ܒi�̂����A��i�̋�i���L���ʁA���i�̘Z�i���L�����ł���B���̓��̋L���̊��t�͎��̒ʂ�ł���B
�@�O���\�l�����i�l�ʁj
�@�����A��i�ځi�S�s�j�u�ԁv�g���M�q�i����܉�j
�@���O�i�ڍ��[�u�푈�Ɛ_�o�v�i�O�j������Y
�@���l�i�������u�s�������̌��R�v�i���j����D�v
�@���ܒi�ڍ��[�u�ߐ����{�����j�v���x�h��
�@���Z�i�������u�ԕv�G�L�v�i��j��ȔĔ�
�@�����i�ڃ��W�I��
�@�O���\�ܓ����i���j
�@����A��i�ځu�ԁv�i���Z��j�g���M�q
�@���O�i�ډE�[�u�����̐V�����v�i��j��㏇��
�@�����@�@���[�u�Ȋw�����ً}��v�i��j�R�{���Y
�@���l�i�ڒ����u�ԕv�G�N�v�i���j
�@���ܒi�ډE���u��̒m���w�v�i��j��؏����G
�@�����@���[�u�ߐ����{�����j�v
�@���Z�i�ډE���u���̏ꏊ�v���i��
�@�����i�ڍ����@�o�嗓
�@�����A��i���W�I��
�@�u��ȔĔ��v�͂��������Ȗ��ł��邪���̃y���l�[���B�\�l���t�͖{���O�i�O�O�s�A�\�ܓ��t�͎O�i�l�s�ł������B
�@��C�̌�܂��u�ԕv�G�L�v�̋�X�����Ă�܂����ɋL�^���Ă��������B
�@�u������Čł��Ȃ����n���^�r��E���ŏ�肩�܂��ɍ������낵���̂���������B�v
�̏��������Ŏn�܂�u�����͌��N���B�ߏ��̋q���ԏ�܂ŏ悹�čs���B�v�ŏI���B�����ɉ��̂��u���P�J�v�Ƃ����n�����o�Ă���B����́u�����P�J�v�̉e���ł͂Ȃ��̂��B���ܓǂ݂������ĉ���Ƃ���肫��Ȃ��B�ԕv�̐����͉悢�Ă��邪���A���e�B���Ȃ��B�S���̋�z�ŏ����������B���Ԃ�����ł��Ȃ����A�����̐���������������ӗ~�I�Ȃ��̂��Ȃ��B�����Ĕ�]���_�͂��炳��Ȃ��̂ł���B���������̊w�|���ɂ͑����ς����L�҂����Đፑ�̏��������ɋ������������̂ł��낤�B
�@���іΕv����̒����u�v�����^���A���w�m�[�g�v�ɂ��{�{�S���q�́u�n�����l�X�̌Q�v�ɂ��āu�n�҂ɑ��Ă����ċ����C���̋U�ł��鎖�A�U��̑������������ċ��鎖���͂��������v���v�Ə����A�u���͍Ō�̈�߂������Ȃ��珑�����v�Ɠ��L�ɋL���Ă���Ƃ����B�{�����u�����Ȃ�������邱�Ɓv�����i�u���}�b�v�ɂ��Ă��邪�A���Ƃ́u�����Ȃ��珑���v�Ƃ������Ƃ����͂܂��w��ł��Ȃ������̂ł���B
�@�Z�����܂�̎��͂��̎��܂��\�Z�������Ƃ͂����A�\���Łu�������_�v�֔��\�����u�n�����l�X�̌Q�v�Ƃ͉���Ƃ����Ⴂ�ł������낤�B�i�S���q�Ɣ�r����Ȃ�Č����܂������悾���B�j
�@�V���Ђ����\�~�̏��ב֓����̏������Ƃɓ͂����B�����̉Ƃɓk�H���鎄�̊�s�����Ԃ�͂��Ȃ艓���܂Œm���Ă����B�����̉ƁA���Ȃ킿�A���̎��Ƃ͎O�㑱���č��Ƃł��������A���̖���ɂ́u���}�T���v�̊Ŕ����������̎��̑傫�ȊŔu�ĕ���v���f�����A�����������ꂳ���Ă����B����������ďf��̉Ƃ͑K�����c��ł����B�����A�����͈ꖇ�A��K�������Ǝv�����A����𑩂ɂ��Ď����ė��Ă͂Ȃ��܂ɖ����Ŕz��{��ꂽ���̂ł���B�ĕ���͕���̂͂������A�����������R�[�h�R���T�[�g���Ђ炢�āu�֕P�v��u�~�̗��v�Ȃǂł��܂����A�J�j�̂��h�W���E�̂�ɖ������Ă����B
�@�u�ǂ�Ȕn���Ȃ��Ƃ������ĐV���Ђɖ��f�����������v�Ƃ������ƂɂȂ�A���߂͂���Ȏ҂͂��Ȃ��Ǝ���Ȃ������炵���̂����A����̏Z�����ԈႢ�Ȃ��̂ŁA����Ɣ[�����������������B����ǂ͌����ɑւ���ɂ������ėX�ǂł́u��ȔĔ��v�ł���ؖ������K�v�Ƃ̂��ƁB�n���R���Ȃ���Ώؖ������Ȃ����́A���ǁA���������ꂩ�瓯��l�ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă�������̂ł������B
�@����Ȃ��Ƃ���ߏ��ɂ͔��Ђꂪ���čL�������炵���B�u���̃A�E�g�E���[�߉�������炩���Ǝv���Ă������v�Ƃ����ҁA�u���̔n���A�܂���炩�������v�Ƃ����ҁA���낢�낾�����B
�@�l���̂�����A�Ă���Ŏd�������Ă�����ь������ė]���悤�ɂ��Č����������Ă����B�u��ȔĔ��v���ǂ��̂����̂Ƃ��������Ă���B�₪�Ĕ����͍��~�ɏ��������B���łɂ��̉Ƃł͈��O���N�ɐ펀�҂��o����w���������܂���Ă����B�]�Z�ł���B�����͕��d�̑O�ł���ɂȂ����B���͂����邨����܂��肱���B�����͕������o��B
�@�J����ԁu�ԕv�G�L�͒N��̂��ƂȂv�Ƃ����B���炩�ɈЂ������Ă���B�Ⴂ�������s�������B���͎��݂��Ȃ��l�ł��邱�ƁA�v�����^���A������ǂ�ł�����A�z���ŏ����Ă݂����Ȃ������ƁA�u��L�v���̂��̂����ꂩ��������������Ƃ�b���B
�@�����̊�͌������B�u�N�ꂾ�A���O���w�����Ă���l�Ԃ́v�Ƃ������B�������Ɂu�J���J�����v�̘b�����Ă��ꂽ�ЂƂ��������u�I�H�D�v��u�s�ݒn��v��ǂ߂Ƃ������ЂƂ�����B�������A�����̊���݂��Ƃ��A����������Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂����Ƀo�J�Ȏ��ł����ʂł����B
�@�u����ȂЂƂ͂��Ȃ��v�Ɠ�����B���������͎G���Ɓu�ᑐ�v��u�V�N�v�����݂ɓǂޒ��x�B�����O�́u���N��y���v�̈��ǎ҂������B�����đ�����ǂ݃��V�����w��������������B���̂����̍��^���S��W���Y���̂��D���Ƃ��������͂��Ȑl�Ԃ������B�����͂������B
�@�u�悵�A�����ǂ�ł��邾���Ƃ��Ă������v�B���������Ď蒟�ɉ���珑�����B�����Ď��ǂ͂��d��Ȋ�H�ɂ��邱�ƁA���Ƃ͂��܂�������V���Ă����]�T�͂Ȃ����ƁA�䍑�ւ̕���Ɉ�������������Ƃ�]��ł���Ƃ����ƒ������������B
�@�������̌������������āA���͋�����ɂ������悤�ɂڂ��R���������B�}�ɖ��͊��ɂ������A�O�r�����������v���������B�ڂ̑O�̈ł��g�債�Ă������B���ꂽ����͂̐l�Ԃɂ͖h���悤�̂Ȃ��g���ė����̂������B�Ȃ������͕��z���ė܂����ӂꂳ�����B�C�ɂ��������܂��Ă����B�i�u�H�c���啶�w�v12���A1988�E7�j
|
||||
|
||||
 |
| | �z�[�� | | �r���{�[�`���[ | | �R���� | | �H�c�̖{�P | | �H�c�̖{�Q | | �H�c�Ɖf�� | | ��c�Ð��q | | �g�c�N����̕� | | |
| | �g�c�N����̎� | | ���؏��O�^���쎍�o���� | | �� | | What's New | | �����N�W | | |