 |
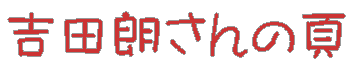 |
|
|
 |
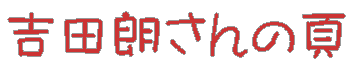 |
| 7 わが旅、わが炎の海は(4) | ||||
|---|---|---|---|---|
四、起床ラッパを吹いて
前号「戦うミクロネシア」の末尾へ、ページふさぎの自作詩をのせたところ、ふたりのひとから感想をもらった。
野上百合(本誌)さんからは「詩を読んで泣かされた」といわれ、木俣滋郎(「第二次大戦海戦小史」著者=朝日ソノラマ=労作)氏からは「吉田さんはなかなかの詩人ですね」という思いがけないことばが、手紙から飛びだした。
もっとも、ふたりは別段ほめてくれたものではないようである。野上さんは戦史にもないような南の小島の、無意味な戦争で死んでいった無名の若者の心情をおもんばかってのようだったし、木俣氏は「なんだ、詩を書いていたのか」という程度のあいさつである。
「詩を書いている」と知らされたついでなので、今回はどうしても奥田さんのことから書かないと気がすまない。例により脱線することを許してもらって一月に急逝した奥田喜已さんのことから書き始めることとする。
奥田さんは一月八日の早暁に亡くなり、二日後の十日現住地の阿仁町の専念寺という寺で葬儀がおこなわれた。「秋田銀行不当差別をなくす会」やその支えとなっている多勢のなかまたちが参列しての葬儀であった。中川前代議士、工藤阿仁町長、横道弁護士や塩沢弁護士の顔も見えた。生前の活動が並々でなかったことを語るものであろう。「差別をなくす会」の佐藤会長から、あとで来た礼状によると「巨星墜つ」という弔電もあったよし。全国の金融のなかまたちや民主陣営のひとたちには大きな衝撃であり、損失であったのである。
弔辞は中川さんをトツプに四人の代表がそれぞれ名文を朗読した。短い時間にこれ程の文を書き、奉書紙に清書している。「金融共闘会議」の鈴木会長のあと私は詩を捧げた。弔詩の注文は葬儀委員長の佐藤賢太郎さんから深夜の電話で入ったものだが、佐藤さんたちが私に詩を「注文」したことがおもしろい。ひとの死にあたって「おもしろい」という言い方は不謹慎であるが、奥田さんをとむらうのに詩があってもよいとした「なくす会」の発想がおもしろいのである。
八日の朝は秋田市は雪こそ少なかったが、零下三度の凍りだった。夜っぴで吹雪はやまず、軒下に、雪が張りついていた。窓や戸はレールに凍りつき開閉に苦労した。そして十日は突如、豪雪が見舞った。
恵美子夫人や葬儀委員たちが奥田さんの急死に直面し、通夜やら火葬やらと不眠不休で活躍し、悲しみと疲労のもとで葬儀計画を練ったとき、折しも、この吉田を思いだしてくれたのがおもしろい。
奥田さんは音楽を愛し読書好き、文も書くひとだったのである。私の「暗い時代には重い詩を」という主張を理解してくれていたひとだったし、私の詩を「好きだ」などと仲間に宣伝してくれていたのである。だから奥田さんは吉田から詩を読んでもらったらうれしいだろう、と葬儀委員たちが考えてくれたのであろう。
そういう奥田さん(たち)の友情に感謝をこめて私はこれまで二編の詩を書いた。一編は八四年二月発行の「ひろば」七四六号に載った「しなやかに、風にむかって」と、もう一編はむかしむかし書いた詩である。この「むかしむかし」の詩は、当時の全国同人詩代表詩選の本にのった。私はこの詩を奥田さんに見せる機会を失なったまま、詩集そのものも私の手許から消えてしまった。書名も題名も思いだせない始末だが、主人公が毎晩おそく帰って来てラーメンを食べている詩だった。息子にそれが父だと思われていることに対して自虐やさびしさをかこつ銀行員。その生き方、生活感情をあぶりだしたつもりだったが、「感謝をこめて」どころか「だし」にして自分のへたな詩を補ったといったところだった。それで奥田さんに見せることをはばかったのであるが、しばらくは会うたびに「見せろ」と要求されるのだった。
そういう不実の人間を「詩人」などと一人前に扱い、心を許してつきあってくれた奥田さんは、実に大きな人間だった。労働組合の運動や民主運動の戦いにいつも「文化」の問題を重くおいたひととして特筆したいひとである。
葬儀のあと、その「ラーメンの父」を失なったふたりの子息と会った。当時小学校二、三年だった男の子たちはりっぱに成長し、足の長いたのもしい青年になっていた。「ラーメン」の話をしたら「高校に入るころまで、お父さんって給料をもって毎月一回家へ帰ってくるひと、と思っていた」と真剣な表情で語ってくれた。
秋田銀行の人間差別の問題は冷たい鉄の扉のように人間の心を暗くする。賃金、勤務、転勤など実に不当な差別をしており、地労委や地裁で次第に明らかにされつつある。この人たちの子どもや夫人、家族たちの精神の苦痛、生活の苦闘もぜひ聴いてもらわねばならない。
急ごしらえの私の三つ目の詩の一部(全文六十行)を次に掲げ、奥田さんを哀悼することとしたい。
「風は峠を越えた」
(奥田よしみさんを送る詩)
ひゅう、ひゅうと風が泣いた
泣きながら風は峠を越えた
しぃん、しぃんと雪も泣いた
泣きながら雪は空を蹴った
六日、寒の入り
七日、七草
やがて八日、夜が明けると
この朝、風は戸をたたいた
ともに戦った同志に
清例な朝の来たことをつげるために
この朝、雪は山に降りつもった
ひとびとの屋根に降りつもった
ともに旗を進めた戦友の
家々のぬくもりを散らさないために
奥田さんには
別れのことばはなかった
奥田さんはこの朝、みんなに
起床ラッパを吹いたのだから
(以下略)
もう一つの戦争
前記、戦史研究家の木俣滋郎氏の手紙に「第四艦隊司令官小林仁中将は釣りばかりして怠り、トラック島被爆の責任をとらせられ、この地位を追われたそうです。」とあった、さもありなんという気がした。第四艦隊摩下の司令官の釣糸の先についた浮子よりも軽かった私に、司令官が何をし、なにを考えていたかなどはわかろうはずもないが、思いあたることがないでもない。しかし「釣りばかりする」司令官が怠け者で、釣りをしないで戦闘準備に狂奔する司令官が果たして働き者なのかどうか。積極的に戦争に反対し、終結させるための行動もあったはずであるから。
木俣氏の「海戦小史」によれば四四年二月四日、米偵察機はトラック島に戦艦一、空母二、重巡五ないし六、軽巡四、駆逐艦二十、潜水艦十二隻、その他商船無数が停泊していることを確認したという。
この日、二月四日、作家窪田精は春島の作業隊にいて、紙芝居をやるため「指導部」の事務所に来ていた。昼休みには入江の砂浜で、汐招き蟹を追った。「連合艦隊は何を考えているのだろう」と思っている矢先き、米偵察機がゆうゆう頭上を飛んでいったのである。
この日、夏島にいた私は駆逐艦「野分」の爆雷員と深度九〇と百一〇について若干の議論をしていた。どんな議論だったか忘れたが、軍極秘できた書類の解釈についての見解の相違だった。そのとき一万メートルの高空を機体を光らせながら南から北へ飛んでいくB24をふたりは見上げた。なぜか全く無抵抗。これが敵機だとは信じられない程、一発の砲弾も撃たれなかった。
結果論かもしれないが、マーシャル群島が落ちた時点で、しかも敵偵察機の飛来を許した以上、大攻撃は目前にせまったと判断すべきであった。米軍は「しめた、カモだ」と叫んだのは本当かもしれない。
二月十二日、マーシャルを発したエンタープライズやヨークタウンなど九隻の大航空艦隊が、十七日大攻撃をかけたとき、たしかに連合艦隊はパラオに退却していて助かったが「那珂」「太刀風」を初め第六艦隊の旗艦「平安丸」や「香取」その他数十隻の大損害を出した。トラック島はこれをもって中部太平洋基地としての機能を失なうのである。
戦力の差はそのまま戦局を左右する。必要な措置を怠ったとしか考えられなくもないのである。もっともこのとき助かった連合艦隊といえどもやがて葬り去られる日がくるが、戦争を続けている以上は当然の帰結だった。このことは、あとでも書くが、「ポツダム宣言」をもっと早く天皇が受諾していれば広島、長崎への原爆を防ぐことが出来たし、土崎を空襲から守ることもできた。
さて、忘却の彼方からトラック島の攻防戦をひきだし、書き進めて見たが、話は尽きるものでない。スペイン系の島民の娘と恋に落ちた上官が戦死して手をやいた話、通信員が米軍の放送を傍受し、聞かせたことが知られ、「要注意人物」としてどこかへ「転勤」させられた話など断片的な思いでがよみがえってくる。次に「もう一つの戦争」を記して「わが旅」の項を改めることとしたい。
戦後、長いあいだ私は、こだわっているトラック島での一つの事件があった。その船の名は「ケンショウ丸」だったか「キクカワ丸」だったか判然としない。いろいろ調べたり聞いたりしているがいまだにわからない。資料も手に入らない。小説家だったらこの事件を小説にして告発することもできよう。マンガ家だったら日本海軍の首脳をマンガ的に画くこともできよう。この事件では、班こそ違うが同じ部隊から三十人も殉職者を出してしまった。
この六千トン級の船が爆発を起したのは四三年の八月か九月のような気がする。内地とちがい季節のない常夏の島だから、暑いさかりとか、紅葉のころとかという季節感がない。パンの本の実のる頃やマンゴを食べたころは記憶にないでもないが、ほとんど濃霧の瀬戸内を、手漕ぎで行く小舟のようにわからない。
「青錆びた古い小さな貨客船。そのむかし旭日の軍艦旗をかかげ、たった一基の九三式機銃で必死に米軍機と射ちあいを演じた船だったかもしれない――」(木俣滋郎著「残存艦船」)
戦時中、「帝国」に働かせられた大小の貨物船。あるものは潜水艦に追われて被害、あるものは空襲で被爆、文字通り海のも屑となり、あるものは生き残った。その生き残りも「青錆びた」船体をさらしている。おそらくは、いまごろ、大半はスクラップとなり、長い「一生」を終えていったことであろう。
太平洋戦争の原因と責任が問われている今日、トラック島のもう一つの戦争、すなわち千とも二千ともいわれる尊い人命を、一瞬にして吹きとばしたこの貨物船の爆発事件の真相と責任は追求されたものかどうか。
大空襲の日よりすくなくとも半年前、夏島に入港して来た貨物船が、荷揚げを始めてまもなく船火事を起した。同船には爆弾、爆雷など爆発物のほか、カーバイト、食糧など軍需品を満載していた。大消火隊が編成され、船上、船外から必死の消火がおこなわれた。夜に入って火勢は劣えるどころか、海上の大きな火の玉は、さながら南十字星をも焦がすかと思われた。その時、各部隊へ増援の命が下り、当直を除く非番の兵が桟橋に駆けつけた。ダイハツその他に乗り組んで現場へ急いだがそれは死出の旅となったのだ。
科学を信ずる司会官や参謀だったら、この火勢と船荷から判断して撤退させたと思う。私でさえ部隊長伝令をしながら、そう考えたのだから。
案の定、払暁、轟然大爆発を起こし沈没した。各部隊とも翌朝の点呼はクシの歯がかけたようだった。死者、不明者の確認に数日かかるといういたましさだった。
その日から交替で海に浮かぶ死体を拾い集める作業にかかったが、戦闘服、戦闘装備のからだをゴムまりのようにふくらませ、舌を噛み切りうつぶせになって波面に浮かんでいた。その爆発の凄さには地獄を見た思いがしたものである。
名もなく派手な戦史も残さず国に殉じたこれらの若ものの鎮魂と慰霊は、総理大臣の靖国神社参拝などですませられるものではない。
洋上で船が雷撃され沈没すると、「損害一隻」で片づける。乗員が何百人いようとも作戦上は「一隻」か「軽微」だった。人間無視も甚だしいといわねばならない。
いまトラック島環礁の海底は、何も知らない観光客の遊び場となっているという。海中には輸送船の墓場もあるので近づく人間もいる。日本の若者よ、その墓場に「ケンショウ丸」とか「キクカワ丸」という名の船が悲痛な傷みを負って横たわってはいなかったか。(「秋田民主文学」10号、1987・7)
|
||||
|
||||
| 8 わが旅、わが炎の海は(3) | ||||
|---|---|---|---|---|
三、戦うミクロネシア
七月二十六日に「地人会」の朗読劇があった。(夜・秋田市の児童館)詩の朗読は自作・他作を問わず、なかまたちにおだてられやってきたが、佐々木愛や渡辺美佐子ら名優による「この子たちの夏―一九四五・七ヒロシマ・ナガサキ」には深く頭を垂れ聴き入った。連れていった小二の孫も席から離れず、じっとこの原爆朗読劇に見入った。へたな芝居とちがい、手記の真実味が強くからだにせまるのである。
役者だから朗読がうまいのは当然だと思いつつも、ヒロシマ・ナガサキの悲劇をくり返すまいという心に、原爆で設されたり、殺されかかったりした母や子どものウソ偽りのない手記が乗りうつっての演劇だから胸がえぐられてしまう。
幕が下りて会場が明るくなっても、しわぶきひとつなく、すぐに立つ者もいない。観客は若い人が圧倒的だったが、それぞれ戦争について、その生と死について考えたにちがいたい。
大きなハリの下敷きになって助けを呼ぶ少女に、手を貸さなければならない三、四人の海軍兵が、どうしても動かないハリにあきらめ、その場を立去る場面を私は自分がさいなまれているように顔をほてらせて聴いた。その兵らが去ったあと被爆した母が戻り、最後のちからをふりしぼる。そしてハリをかつぎあげ、娘を助けだす。それをみていた姉娘の手記である。私は暗がりで恥ずかしい思いをこらえていた。燃えさかる広島を駆逐艦上からいたずらに望遠鏡で「敵機警戒」しながら日をすごし、手を貸すことを怠った同罪の人間だった。ヒロシマは私の原風景であると同時に、死ぬまでの傷痕なのである。この夜は孫がいとしく我がままをきいてレストランへ入ったものだった。
そのヒロシマについてあらたな思いを起こすことがあった。ヒロシマの語りべ佐伯敏子さんから「呉空襲記」が送られて来たのである。呉は私の乗組んでいたふねの母港だったから呉は当時海軍管理都市。原爆こそ落ちなかったが敗戦の日まで五回の大空襲を受けた。延べにすれば艦載機二千百七十機、B29・24爆撃機は六百十機。二千七十一人の死者を出し、街は灰燼に帰している。なかでも戦死者八百人を越した呉沖海空戦に私の艦は遭遇したし、B29八十機による猛爆で全市火の海となった七月一日(一九四五)の空襲は、その四日前に上陸しているのだった。
「この本の中には思いだしたくないことや、真実をもう一度考え、語ることの大切さがある」と佐伯さんの手紙にあった。佐伯さんからくる手紙はいつも示唆に富んでいて教えられる。ことしも割山地区の「平和夏まつり」には佐伯さんから送られた「原爆瓦」が展示され関心をあらたにした。佐伯さんは被爆者の証言を映像として記録しようという、広島平和文化センターのビデオの証言者の一人である。
海上包囲デモなどの抗議運動のなか、明らかに核を塔載したアメリカの戦艦「ニュージャージー」が八月二十四日に佐世保へ入港した。ごていねいにも横須賀へ空母・呉へは駆逐艦が押しかけ入港し、といった強引さであった。いずれもトマホークを積んでいる。
レーガン政権になってからの強引さは目にあまるものがある。日本や朝鮮半島への核持ちこみもそうであるが、ミクロネシアに対する懐柔策というか強引さは、ナチスがヨーロッパを席捲した時のような侵攻ではないにしろ結果において変らない。
ミクロネシアは地図をひろげればわかるように広大な西太平洋に浮かぶ二千以上の島からなる平和の楽園である。「海で暮らすならダイバー船でおじゃれ、北はマリアナ、南はポナペ」などと歌われた。そのマリアナ諸島の南にパラオ島、そして西へトラック島、ポナペ島、マーシャル諸島、タラワ、マキン島と横に連らなっている。人口は合わせて十五万という。
アメリカはこの地域を北マリアナ連邦(サイパン島など)マーシャル諸島(クエゼリンなど)ミクロネシア連邦(ポナペやトラックなど)パラオ共和国の四地区に分割支配して来たが、その信託統治終了後は北マリアナは「自治領」、他り三地区は「自由連合』としている。
実はその「協定」は双方の合意がないと廃棄できないということになっているので、住民は協定が気にいらないから破棄しようにもアメリカが「OK」しなければどうにもならない一方的なもの。つまり永久的協定だ。経済援助のほしいこの島々は援助と引きかえに軍事と安全保障をアメリカに委譲した形だ。国連はアメリカに屈服していくこの小国を指をくわえてみていたにすぎない。
パラオ共和国は一九八一年に自治政府が発足した。世界最初の非核憲法をもつ国として注目されたが、こんどこの小さな共和国はアメリカから今後五十年間に経済援助を十億ドルに増額するという約束とひきかえに核持ちこみを呑んだのである。
しかもフィリッピンのスピック湾の海軍基地やクラーク空軍基地を失ったときに備え、アメリカはこの一月、パラオに海軍基地と空軍基地をつくる予備協定に調印させた。アメリカ民主主義は「住民投票」という形式はとるが、エサをまいて住民の意志を眠らせることを常套とする。
住民投票にあたってはアメリカは一人当り五百ドルの資金を使ったという。パラオ国憲法は空洞化され、核軍事化に道をひらいた。アメリカは安い買物をしたのである。パラオには私の青春を共にした戦友が眠っているのである。
アメリカは国連憲章に反してマーシャル諸島のクエゼリン・エニウトク・ビキニ等の住民を強制移住させ、原爆実験、あるいは核ミサイルの着弾実験場に使った。そしてミサイル基地として要塞化しているが、こんどはパラオを巨大な海軍基地としてつかうのである。
クエゼリンは旧日本軍の前進拠点であったが、こんどはアメリカの国際戦略拠点となった。一月十二日の新聞はその「象のオリ」なる巨大な通信情報収集等のアンチナ、直径五十メートルのレーダードーム、長大な滑走路、ミサイル基地などを写真入りでスクープした。
晩秋から初冬の瀬戸内の海を、去年は何度か往復した。宇品と能美島、宇品と江田島、宇品と呉の連絡船でである。戦時中、漁船が触雷し海に香まれていくのをみた。青い海だったが、それはいまも変らない。宇品からは多くの思想犯が南の島へ強制労働に送られていったという。青い海はその船や人の姿をうつしとっているにちがいない。
だがミクロネシアの海は、はるかに美しく澄み、七色にやさしく広がっている。窪田精「トラック島日記」はこう書く。
「向こうの夏島や秋島のまえの海はいつものように軍艦でうずまっていた。戦艦も巡洋艦も駆逐艦もいる。潜水艦も浮かんでいる。五六十隻はいる。軍艦はしだいに強くなってくる日射しの下で浅黄色に光っていた。それらの軍艦も昨年二、三月ごろのガダルカナルの撤退作戦いらいもう長いことそこに碇泊したままである。」
一九四四年二月十七、八日の米軍のトラック島大攻撃前の描写である。
窪田精は「二月四日の朝はじめて目にした米軍の偵察機であった」とし、数十隻の連合艦隊が湾内に碇をおろしていることについて「うごかざる艦隊か」「連合艦隊はなにを考えているのだろう」と「そんな会話を交わしていた」のだそうだ。
窪田精は戦時中反戦活動のかどにより十九歳のとき、横浜刑務所に入獄、青島の囚人部隊に送りこまれ、強制労働させられたのである、獄中五年のうち三年八カ月をトラック島で生活し、敗戦後帰国した。一時は千五百人をこえた囚人部隊は生存わずか数十名であったという。ほとんどが餓死だった。「トラック島日誌」(光和堂刊)は「みんな飢えた野良猫に変化」し、「死とたたかい」「赤痢と空襲におびえ」「味方どうし殺し合った」悲惨な「死の島」であったと告発している。
二月十七、八日の大空襲は後に歴史家により「日本海軍の墓場」と評価された程の大痛手を受けたものだが、窪田精はさすがに刻明、精致な筆で、読者を戦場へ連れもどす。
「島の北端の陸上基地の滑走路のうえあたりからはじまって、島の西海岸を低空で一直線に駆けぬけ、海岸線ぞいに島を一周するように、機銃掃射をあびせてゆく。それがあとからあとからつづいた。たまがよくあると思うほどだった。そして島の周囲を一周するとまた、キューンと上空に駆けあがり、方向を変えて、となりの夏島のほうに向かった。逆に夏鳥をさきにすませてこちらにむかったりするものや、青いきらきら光る海をこえて、真向いの楓島や竹島や水曜島のほうからとんでくる編隊もあった。」
「全速をあげて、湾内を逃げまどっていた巡洋艦や駆逐艦が、四方八方から米軍機に追跡され、機銃掃射や魚雷をあびて火を吹き、その黒い姿をつぎつぎと海中に没していった。」
そのとき窪田精は春島、吉田朗は夏島にいた。(関係ないけど)「トラック島日誌」によれば窪田精は一九四五年、十一月二日トラック島を出港し、六日後の十一月八日久里浜へ無事帰投している。輸送艦は駆逐艦「波風」であった。「波風」の話はあとで書きたいが、敗戦まで私は電測員として乗り組んでいたふねである。
窪田精のような不幸な人間を出さないためにも、また何万、何千万が苦しみ、死んでいった人々に代って、われわれはいま何をすべきか、常に関われているような気がする。
戦争の名残りは確実に消えていっているがこの環礁の「墓場」はいまもそのまま残っているという。米軍の爆撃を浴びた日本の艦船はその数は七十とも百隻ともいわれる。エメラルド・グリーンの波がそれを洗っている。
いささか感傷的な鎮魂の詩をこの項の終りに掲げ、私の「炎の旅」をまた続けることとする。
「流れる雲に」
流れる雲に聞いてみたい
熱帯ブルーの海
リーフが包む岬のあたり
沈船のマストは
いまも朽ちずに
波まにあるかと
流れる雲にしっかと見てほしい
マングローブの林にかくれて
桟橋があり
そのたゆたう波で
もはや渚の血の色は
洗われているかと
流れる雲に知らせてやりたい
そのむかし 太平洋戦争の末期
ニッパ椰子の葉を背につけて
グラマンの機銃掃射を浴びた日本兵が
何百何千と死に絶えていった
太平洋の戦場の物語りを
(一九七八・平和美術展)
(「秋田民主文学」9号、1986・12)
|
||||
|
||||
| 9 わが旅、わが炎の海は(2) | ||||
|---|---|---|---|---|
ニ、いわゆる「海軍生体解剖事件」
ことしの多喜二祭はいろんなことが重なり忘れられないものとなった。とはいえ、ことしの催しが特別変っていたというものではない。もっとも、ことしは活躍中の文芸評論家佐藤静夫が一九六五年以来の再来秋の講演であったし、秋田県の民主文学の旗を進めてきた和泉竜一さん(県南民報主幹)が多喜二祭賞を受けたということもうれしいことであった。
たしかに秋田市でひらかれる行事は多くなって来たが、二月の厳寒に中規模程度の文学的集会がひらかれるのは皆無なことだ。
とくにことしは民主文学支部の計らいで、佐藤静夫や作家工藤威らとヒザを交えながら、じかに話を聴く時間があった。それは文学を志すなかまには有益であったにちがいない。
この日の「朝日歌壇」に「被差別の重荷に耐える集いなり意義説く生徒耳たぶ染めぬ」(近藤芳美選)という歌があった。多喜二もまた当時(一九三〇年代)共産主義者として、天皇制や戦争と闘い、帝国主義官憲に差別され迫害されたひとりだった。多喜二の文学に親しみ思想にふれた時、その重荷を思わない人はいない。
また「戦犯という語彙すでにして死語というその死語負いし夫と生き来ぬ」(同)という歌もあった。私は一瞬、数多の戦死していった若い日の友を思い、またそれらの頼みを果たせなかった自分の不実を責めてみた。そして疎遠になっている戦友たち、BC級として捕らわれ、いまは静かに余生を送っている歌人H氏を思い起こした。H氏からは近詠を記したハガキが雇いていた。
二月二十三日前後はまた、私の奥歯の痛みがひどく、知り合いの歯医者(三月死亡)が、からだをこわし寝ていることから治療もならず、じっとがまんの子となりこらえていた。だがその痛苦を忘れさせる衝撃波が私のからだを抱きこんでいた。それはまた世界を震憾させていた。フィリッピンの繰上げ大統領選後の情勢変化である。
その日、新聞は次の通り伝えた。
「比軍主脳が反旗――事実上のクーデーターか。大統領退陣を要求。反乱拠点に支援の群衆」(秋田さきがけ)
「マルコス大統領に反旗――司令官とは認めず。軍人に同調呼びかけ」 (朝日)
「押しとどめることのできない何かが動き始めた」 (赤旗)
「マルコス政権窮地に」(読売)
翌二十四日の見出し。
「反独裁の世論、マルコス体制分断」(赤旗)
「比国防相ら基地占拠――大統領派の戦車出動。民衆通行を阻止」(朝日)
「フィリッピンの長い歴史をみても民衆が反乱軍を支持したのはまれなこと。人々の表情は予想以上に明るく国防省周辺には華やいだ空気が漂っているという」(さきがけ「北斗星」)
「野党勢力は勝利気分――基地周辺に数万」(読売)
この日のテレビ報道はとくに生々しく印象的なものだった。一九七五年四月三十日の「サイゴン突入」を思わせる感動的な映像だった。
国営放送は反マルコス派が占拠、若い女性アナウンサーがマイクに話しかける。「これが最初の自由放送です」「きょうから国民のための放送をします」とニッコリ笑う。画面の外側から拍手が聞こえた。不思議なことにこの革命は秩序だっていた。
「亡命用の飛行機を用意し、出国を促す」放送もあったとニュースは伝えた。「アキノ大統領」が現実のものとなりつつあった。
「将軍が相次ぎ寝返りしている」と報道した。時間の流れと共にマルコス政権の終えんが近づいていることを感じさせた。
アキノ夫人は「すべての人々に正義をもたらすことを誓います」と演説し「人民の民主的政府をつくる」と声明した。また「まだわれわれの支援を決めていないひとは、早くいっしょになって美しい祖国を再建しよう」とコリーコールにこたえた。そして「自分こそフィリッピンの国民に選ばれた唯一の大統領である」と呼びかける。「国民はアキノ政権に税金を納めるように、さらに各国政府が同政権をすみやかに承認するよう」放送した。
アキノ大統領の歴史的な発言が続いた。民衆は熱狂し、これを迎える。私のメモを続ける。
「苦難の時代は終わった。われわれは自由と権利を得た。平和と傷をいやす時がやってきた。マルコスに忠誠を誓った鎮圧軍のみなさん、民衆や民衆の軍隊に銃を向ける代りに、その手を国家再建のため、私にさしのべてください」と訴えた。
「国家再建への道は団結」とものべた。
「なる程、経験ではマルコス氏にかなわない。私には国民をだます経験も、盗みをすることも、政敵を暗殺する経験もないから」
「(政権交代のために、自由な選挙のために)フィリッピン国民は勇敢に、自己犠牲的に、いかなる困難にも劇的に、命をかけて、献身的にたたかった」と民衆をたたえた。実は「バヤン」(新愛国者同盟)などの運動。
強大を誇るかに見えた独裁権力は崩れていった。民衆は邪悪の中身を知るとたちまち敵にまわる。敵にまわったが最後、蜂起した民衆は命を惜しまない。素手でも戦車に向かっていく。
海と太陽の国の民族は楽天的で素ぼく。純真だ。この民族を裏切り、だまし、ペテンにかけ、もうけようなどという恥ずべき者がいたとしたらいつか海へたたきこまれる。政府も日本企業も二省三省しなければなるまい。侵略、侵攻していった日本陸軍のはしくれ、従兄がレイテ島で戦死しているだけに、洋上はるかな隣国フィリッピンの平和を願わずにいられない。(三月五日、元共産党議長ら最後の四人を釈放したことにより、政治犯の監獄は空室となったという)
さて、「小説書き」でもないのに佐藤静夫らから、小説の手ほどきを受け大いに感銘するところがあった。
「わが旅……」は小説でなかったことを幸せとする。小説は軌道脱線は許されないだろうから。
以上、どうしても書きたくて。
では本題に入り「若い日の戦友」と「戦犯」を考察してみたい。
侵略者、日本海軍のはしくれ、私の戦友の一人、埼玉県美里村のF氏は、いわゆる「海軍生体解剖事件」の起った一丸四四年の初頭、トラック島第四海軍病院の当の現場に勤務していた人間である。彼も私もすでに前年に夏島に上陸していたし、史上名高い四四年二月のトラック島大空襲は共に遭遇した間柄である。
この「生体解剖」といういまわしい最初の「一月事件」は私は知るよしもなかったが、「米軍捕虜」がいたことは情報として胸にたたんでいたものである。
戦後、私はF氏の生死を確かめると同時に恐るおそる「あれからどうしたか」を問い合わせてみたが、ついに彼からは心をひらいた返事をもらえなかった。その理由は「おれは文が書けないから」あるいは「記憶が不確かだから」だったが、本当の理由は「いまさら戦友をおとしいれるようなことはいいたくない」だったと解釈している。彼が私如きに真相を語ョても何の得があるわけでないし、傷が痛むだけだということを私は知った。彼の戦後の生き方をうかがい知れば判断がつくのである。とくにBC級戦犯には「無実」あるいはそれに近い戦犯が多かったのだから。
旧満州を舞台にしておこなわれた関東軍細菌部隊(七三一部隊)の、戦慄すべき恐怖の「生体実験」は、いまでは知らないひとはいない。あの悪名高い殺人鬼どもの部隊長たる石井四郎は無罪だった。石井ばかりでなく、「七三一」は戦犯に値いする犯罪はなかった、ということで部隊そのものも問われることがなかった。
アメリカ軍当局との取引きということもわれわれは知っているのである。「七三一部隊」を名乗る戦友会はいまも堂々と会合をひらいているというが、なかに十字架をひきずりながら目立たない一隅で生きている人もいる。
第二次世界大戦中に
ドイツ人はユダヤ人の絶滅をはかった
だからドイツ人は悪い――
と言ってはいけない
ユダヤ人を収容所から助けたアメリカ人は
ヴェトナム人の皆殺しをはかった
だからアメリカ人も悪い――
と言ってはいけない
収容所から解放されたユダヤ人が
今度はアラブ人に残虐行為を働いている
だからユダヤ人も悪い――
と言ってはいけない
(以下略)
――小海永二「回り燈篭」から
詩人はやわらかい調子で、戦場における殺人の因果関係ともいうべき本質を詩にして読む者を導く。「人間が人間でなく」殺人鬼にさせていく者を暴く。
F氏から断わりの代りに私の好物「小梅」の漬物が送られて来た。その頃、協和町在住の歌人H氏の「浮虜の歌」が「秋田県短歌賞」を受賞した。七一年の冬のことである。私は目を見はった。H氏もまたF氏と同じ第四海軍病院に勤務、しかも語らざる「戦犯」と目されていたのである。
その二十首により私は、それまで読んだり聞いたりしていた「海軍生体解剖事件」の全ぼうなるものの奥底に、光りがさされた思いをした。それは詩人、小海永二が、「戦争と民族」の問題を解いてくれたことと合致していた。
人間の性格とか立場の問題にひっかかっていた私は、苦衷の底で詠じたH氏の心を知ることができたのである。
H氏の痛恨の二十首から、私の拙文を補強するに最少必要な作品を掲げさせてもらえば、次の九首となる。
戦犯の容疑者として逮捕すと武装米兵らわれをとりまく
苛酷なる拷問に耐えしその極を遂に放てる「殺さば殺せ」
ジャックナイフのどにつきあて戦犯の自白迫りき韓国人通訳
戦犯の審議裁くとグァム島に運ばれてゆく暗き船倉
証言に立ちしわが胆定まりて「命令と服従」の理説くごとく言ふ
戦争の枷をになひて刑場に手をふりて行く将のいくたり
内地転送決まりし夜はココ椰子の葉ずれにさめて日本を恋ふ
二人づつ手錠に細まれ降り佇てり横須賀波止場の風肌に刺す
厳しき巣鴨ブリズンの門入りてこれより経ゆく刑期を思ふ
トラック諸島は、中でも夏島は風光美しく、コプラなど実のりの豊かな島だった。東西四キロ、南北に三キロ、周囲が約十三キロもあった。沿岸は椰子やマングローブが茂っていた。幾つもの入り江があり、緑の影が爽涼の海に浮かんでいる。半島と半島とのあいだにかかった道路は、天の橋立に似て朝風、夕風が吹いた。全島が軍事基地化してはいたが、カナカ族と日本人は仲よく同居していた。事実は島民の生活を侵害していたことになろうが。
その海軍病院に私は二週間近く通院した。戦給品をしゃぶりすぎた罰でムシ歯になったのである。ヤシ林に囲まれた斜面に立つ病院は管理棟のほか数棟の病舎があった。広場には巨大な天水桶のあったことをおぼえている。
一九四三年の暮れ、トラック環礁付近で一隻の米潜水艦がつかまった。前号にも書いた通りこのリーフに逃げこめば味方船は安全だった。代りに厳重な警戒をくぐって入るのは至難といわれた。米潜水艦がそのせまいリーフの水路へ潜入してきたのである。たちまち爆撃機が飛び爆雷を投下した。潜水艦はあっけなく浮上した。
トラック島で私は、第四艦隊の機雷と爆雷兵器を扱う記録員を押しつけられていた。物相な係りもあったものであるが「命令と義務」がそうさせた。現物は見たことのあるものとないものもある。私は機雷だとか掃海機だとか防潜網だとか、爆雷投下機だとか浮標だとかを取扱った。爆雷は深度(爆発)九十メートル。百三十メートルの新型もできたが実効の程は知らない。爆雷は戦艦大和が二百個も横須賀から運んで来たことがある。
私の任務はそれらを受信すると部隊長その他に報告し、艦船などの要求に応ずる工夫をすることだった。
艦船の大小と任務にもよるが、投下機一台三個ぐらいから二十個程積んでいたのではなかったか。もしかしたち、この時の潜水艦をやった爆雷も書類上は私の手を経ていったものかもしれない。無関心でいられない。
乗員約五十人が捕虜となり警備隊に拉致された。この情報をたしかに私は耳にした。この俘虜の何人が生体解剖されたかは不明である。五十人のうち約半数は輸送船に乗せられ日本に向かったが、米潜水艦で魚雷攻撃をうけ沈没している。
当時の往き帰りの輸送船団はかならずといってよい程、魚雷攻撃を受け、船団のうちの何隻かは海の藻屑と消えた。制海権はもはやアメリカに代りつつあり、補給危機は重大段階に至っていたのである。
第四海軍病院をふくめ、第四艦隊司令部麾下の米軍補虜の殺人は「虐待のち斬殺」といわれる。その残虐性は次の記録で想像できる。
「本日、実験に同席するT衛生大尉より聞き知れり。毒薬を注射して死亡させた俘虜二名は和歌山班の看護婦たちにより解剖室に運ばれたが、他の二名は消毒所に運ばれ、院長が大尉に命じて焼火箸を用意させ、捕虜の身体を焼き棍棒で殴打し、その後に解剖せり、と」。
これは「一月事件」を記した関係者の「日記」である。「七月事件」は密室ではなく、病院の裏山に病院関係者、現地人という「見物人」がいた。院長は米軍の無差別爆撃非難の演説をしてから、希望者を募り二人の俘虜を突き刺させた。のち首を切ったという。
「七月事件」は海軍病院にとどまらず、負けじとばかりに警備隊でも敢行された。惨劇は防空壕でおこなわれた。
そこでは、捕虜の足の爪をとり、腹部切開をし、虫垂を摘出、大腿部を切開、陰嚢をひらき、睾丸をとった。それから包帯を巻き、のち首を落とした。
補虜は手術後「口をもぐもぐといっていた」し「手にロザリオを握っていた」という。
これら功をあせるエリート軍医どもは、切落とした首を釜ゆでし、「しゃれこうべ」をつくる。気の弱い私には、それは筆にできない。
事件が追求されたのは魚雷攻撃で死んだと思われた補虜の一人が助かっていたことからだった。どんな時代にも、またどこの国にも、うまく立ちまわり自分だけが生きのびようとする人間がいるものである。
「核シェルター」を「愛用」する人間と同じに。事件関係者が補えられ、グアムに送られる。裁判にかけられる間に、米軍にとり入り、虚偽の証言をし、他を平気でおとし、自らを保身し、刑をまぬがれようとする。将官級に佐官級にいた作家岩川隆は
「戦後の医学界をつくってきたのは、ずるく立ちまわった真の戦犯者たちではないか。いまをときめく医学界の権威者の中にも、この生体実験、生体解剖事件にかかわった人物が存在するのではないか」といっている。
H氏もF氏も語ることをさけ、昭和史の現場をつっ走ったからだをひっそりと郷里においている。だがH氏の歌により「戦犯」の凄じさ、その酷虐の一端を知ることができる。
事件とはちがうが映画「私は貝になりたい」はまさしくその事情を表現していたと思う。
「俘虜の歌」は異状体験の緊迫感がよいとか、回顧的だから意義が薄いなどなどの批評があった。
「俘虜の歌」は「人間を人間でなくさせる原因」(前記小海永二の詩から)を憎み、自分を殺人者に仕立て上げた政治のからくりに、怒りを燃やしてうたった、滄州の声、といえないだろうか。(「秋田民主文学」8号、1986・6)
|
||||
|
||||
| 10 くエッセー> わが旅、わが炎の海は | ||||
|---|---|---|---|---|
一、トラック島の波間
一九五四年三月のアメリカの水爆実験で、一躍?世界に名をとどろかせたビキニは、どこか遠い南の島のことと思っている人が多い。戦前、日本の委任統治地の一つ、マーシャル群島の一島だというと「なんだ、南洋か」とたいていの人はうなずく。マーシャル群島はすでに第一次大戦後より「酋長の娘」の唄にうたわれていたのである。
そのビキニから南へ五百キロのあたりにグエゼリン諸島があるし、そこから東へ一五〇〇キロの地点にトラック諸島がある。
戦時中、トラック島の海軍基地に勤務していた私は、玉砕地タラワ、マキン、クエゼリンは耳になつかしい島の名である。クエゼリンは四四年の一月中戦闘が続き、二月四日、ついに守備隊は玉砕した。それまでトラック島から救援物資が補給されていたし、往復する船の名が通信に入るので玉砕を知らされたときは大きなショックを受けたことをいまも思いだす。
どういうわけか、玉砕の二カ月程前、いや一カ月前までも、つまり日本でいう年の暮れから正月すぎへかけて大陸の守備隊(そのほとんどが召集兵だった)が着のみ着のままの姿でトラック島を中継にクエゼリンへ送りこまれた。部隊の下々の私どもまでが疑問に思った程。それは無暴無策といってよい狂気じみた作戦だった。あれは大量殺人でなかったかという印象をいまも捨てきれない。
あのとき、キャッチャボートの船長が、「こんど帰投するときはマグロをみやげに持って来ますから」といって固く握手していった別れが忘れられない。
原爆投下は完成する前から日本を目標にしていたというニュースが、被爆四十年の八五年七月の各紙にのった。それはアメリカ政府の原爆関係文書が大量に手に入ったために明らかになったものだが、その中の軍事政策委員会会議録に「トラック島の日本艦船への投下が最善」という一項があり、私は身ぶるいした。
アメリカで原爆が完成したのは四五年だったと思われるが、もし、その一、二年前に完成していたらトラック島で実験的に使用された可能性がなかったわけでない。
そのころのトラック島は中部太平洋の重要拠点として、やがてラバウルから航空兵力を引揚げてからは絶対国防圏の要衝とされていたのだから。四二年五月から四四年三月までの約二年、私は記録員の仕事につき、非常時には部隊長付伝令を勤めたのであった。
三個の原爆の最初の成功は四五年七月。最初の一発はニューメキシコ州の砂漠アラマゴールドでおこなわれたという。残る二発を投下するために目標の広島、長崎、小倉、新潟の四都市を目ざし、その日から秒読みがおこなわれていったわけである。
四三年のある日、私は基地の情報を読んで雀躍したことがある。それは日本の軍部と科学者が「特殊新爆弾」を発明したといういわゆる機密情報で、例として東京の神宮球苑の三十倍とか百倍とかの面積が一発で破壊されるといった説明があった。
当時は零戦が独壇場といったところで、椰子の葉を騒がす涼風を蹴っては夜襲に出かけ「戦果、戦果」の虚報を打電していたものだ。
対日反攻が強化され、ガダルカナル、ラバウルがあぶないといわれている時でも、トラック島には連合艦隊や第四艦隊が悠々と(そう見えただけ)錨をおろしていたのである。夏島の北湾は戦艦大和や長門が、プルーシャンブルーの海面に影を浮かべていたし、正午になれば長官山本五十六は甲板へ出て白いテントの下で、軍楽隊の演奏を聴きながら昼食をとるといったのどかさがあったのである。
数多くの商船でも娠わっていた。思い浮かぶものからあげると富士山丸、神国丸、平安丸、宝洋丸、愛国丸、さんふらんしすこ丸、北洋丸、伯耆丸、富士川丸、りおでじゃねいろ丸、花川丸など。さんふらんしすこ丸の甲板にはいまも甲板には戦車がのっているそうだが、これらの船はアメリカの潜水艦や駆逐艦に追われおわれながらもトラック島のリーフ(珊瑚礁)へ逃げこめば、もはやそこは安全地帯だった。だが、その多くは四四年二月の米航空艦隊の奇襲で六〇メートルの海底へ沈んだ。
りおでじゃねいろ丸は私も乗ったことのある船だが、空爆を受け沈没していくさまは壮烈なものであった。夕刻近く船首を天に向け巨体が波間に消えるまでを、ぶるぶる震えながら見なければならない私は、この世の終わりが来たと思ったものである。
トラック島には米機がよく偵察に来た。時には連合艦隊がいたり、ときには大船団が、あるいは第四艦隊がというふうに入り替り立ち代り碇泊していたので、アメリカとしては当然無視できない基地として、作戦カードが出来あがっていた筈である。
夏島には根拠地隊の司令部がおかれ、また日本の経済 進出の前進基地として、小学校や映画館、南洋庁などが あり、食堂や商店などの町並みが出来ていた。春島が航空基地、秋島には火薬庫があった。
島民にはスペイン系混血美人がいて、椰子の葉陰にたたずむ煤色や小麦肌の肉体に驚かされた。私は空襲のない夜の、戦利品として補穫したアメリカ映画の上映に関心があった。
「ノポング アンニム」(今晩は)
「コネ ノム」(さようなら)
島民との会話はいまはなつかしい。現在ミクロネシアにできた三つの自治政府は、政治的経済的に苦境にあると伝えられる。真の自由の重さということであろう。
クエゼリン環礁はアメリカの核ミサイル実験場となって久しいが、島を追われた元住民たちが逆上陸したという報道は、核軍拡に反対する世界の反戦運動に大きな感動を与えている。この「座り込み」闘争はアメリカの核戦略を揺るがすものだが、基地反対派は①ミサイル基地反対②クエゼリン島の返還③土地賃貸料の値上げと未払分の賠償を要求している。だが信託統治者のアメリカは高姿勢だという。
一九四四年二月、日本軍の玉砕で、戦火が去った筈の島に、以来進駐し、基地としたアメリカは半永久釣な使用を主張している。日本がかってそうしたことではあるが、この暴挙を許してならないとおもう。
クエゼリンを一蹴した米軍はその返す刀でトラック島に襲いかかった。四四年二月十七日と十八日の大攻撃でトラック島は完全に壊滅したので、その後の原爆の投下は全く不必要になったものであるが、あの攻撃下、われわれが渚のマングローブにつかまりサイパンからの救援機を待った。それも空しく、艦船の沈没は潜水艦イ一六九号をはじめ前記商船など沈没は約百、飛行機は百八十(ほとんど飛び立つ前にやられた)兵の損害は四千以上。地上施設は形あるものはほとんど爆砕、焼失したのであった。
十八日夕刻、米軍上陸の情報が流れ、リーフの数キロ洋上で舟艇が向かって来ていると知らされ、一時は玉砕を覚悟したのであった。思えば戦争は二度とごめんこうむりたい。
いまミクロネシアは米国の信託統治下にありながら、軍事基地や実験場、訓練場になりつつあり、住民の窮乏が問題になつている。少数民族が平和に暮らしていく道はこの世から戦争をなくす以外に方法はない。水産資源がありパンの木が実のり、バナナ、マンゴ、パパイア、椰子の豊かな楽園にどんな軍事基地も、まして戦争は不用である。
熱帯の海ではかって、われわれは大胆な悪業を仕出かした。そして炎によって波間を染め、その結果、多くの同胞がフカの餌食きとなった。あの波間に浮かぶ戦友らを幾つもいくつも拾いあげた地獄の海を思いだすにつけ、いま自分のなすべきことは何かを自問するのである。(「秋田民主文学」7号、1986・1)
|
||||
|
||||
 |
| | ホーム | | ビンボーチョー | | コラム | | 秋田の本1 | | 秋田の本2 | | 秋田と映画 | | 矢田津世子 | | 吉田朗さんの頁 | | |
| | 吉田朗さんの詩 | | 押切順三/自作詩覚え書 | | 詩 | | What's New | | リンク集 | | |